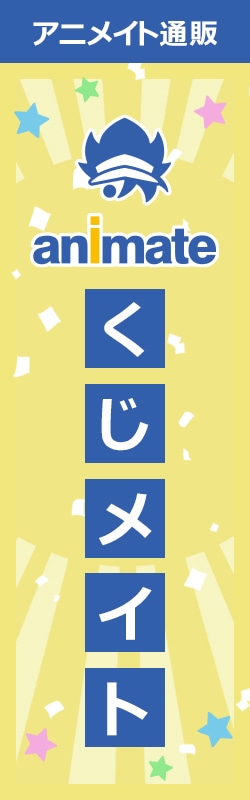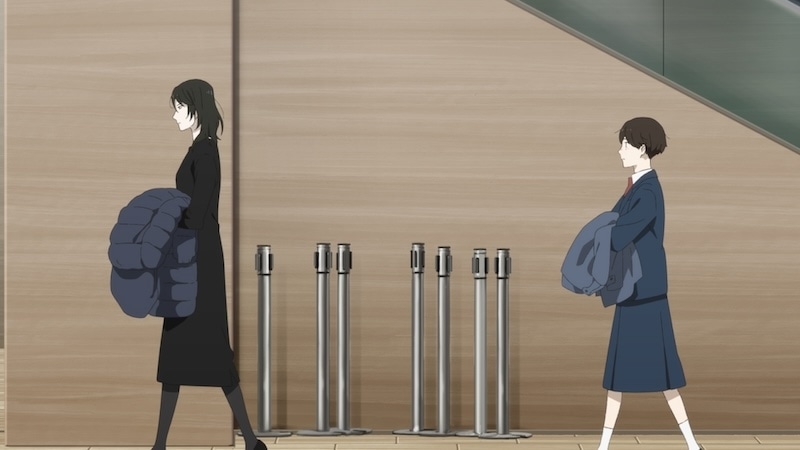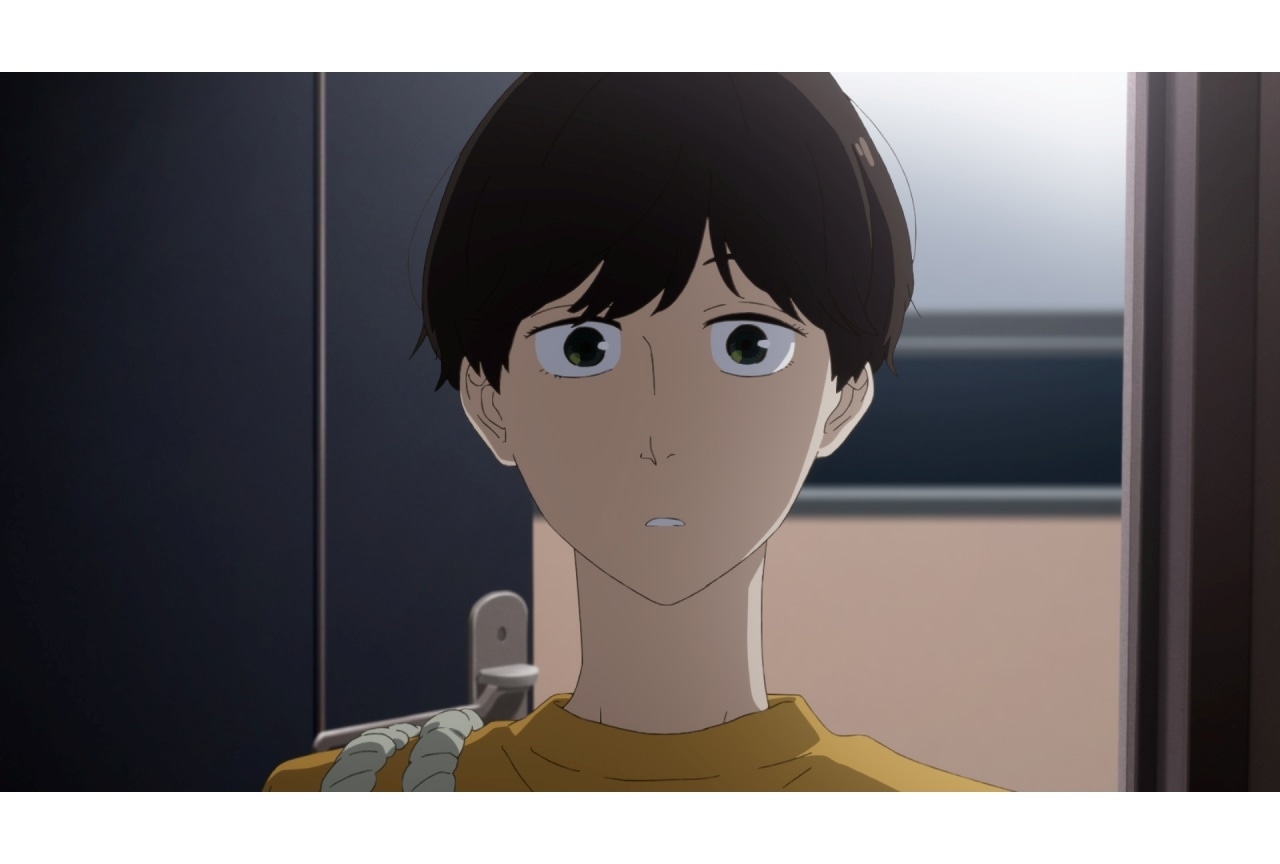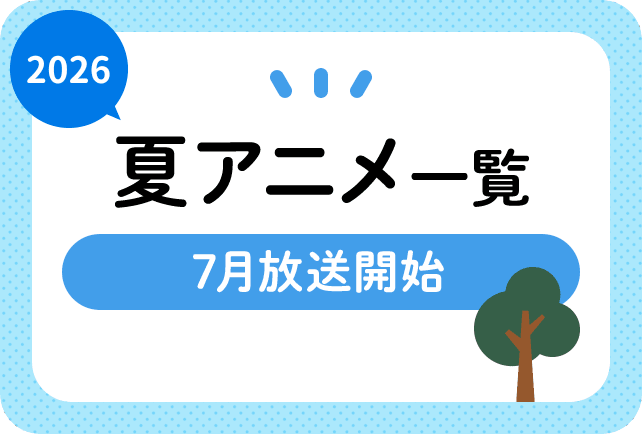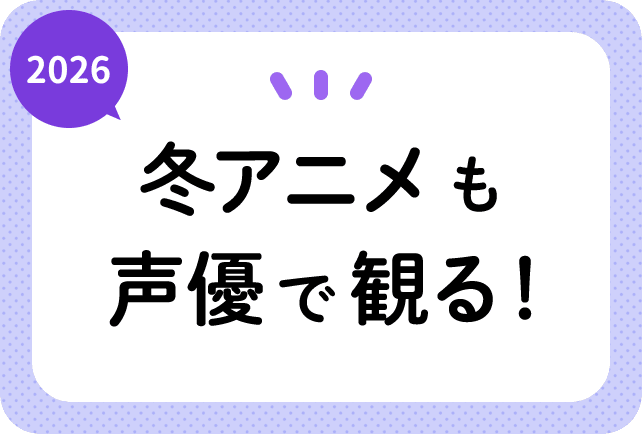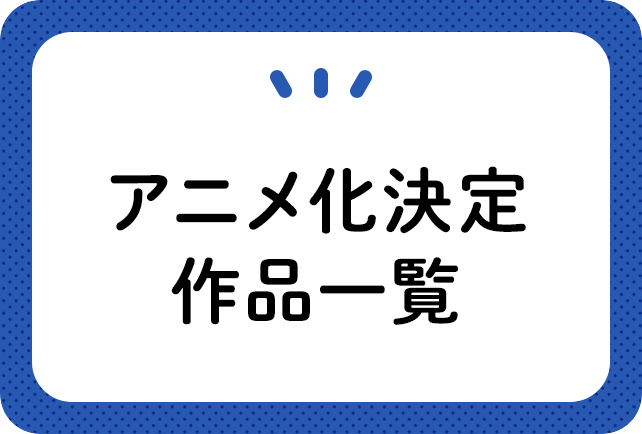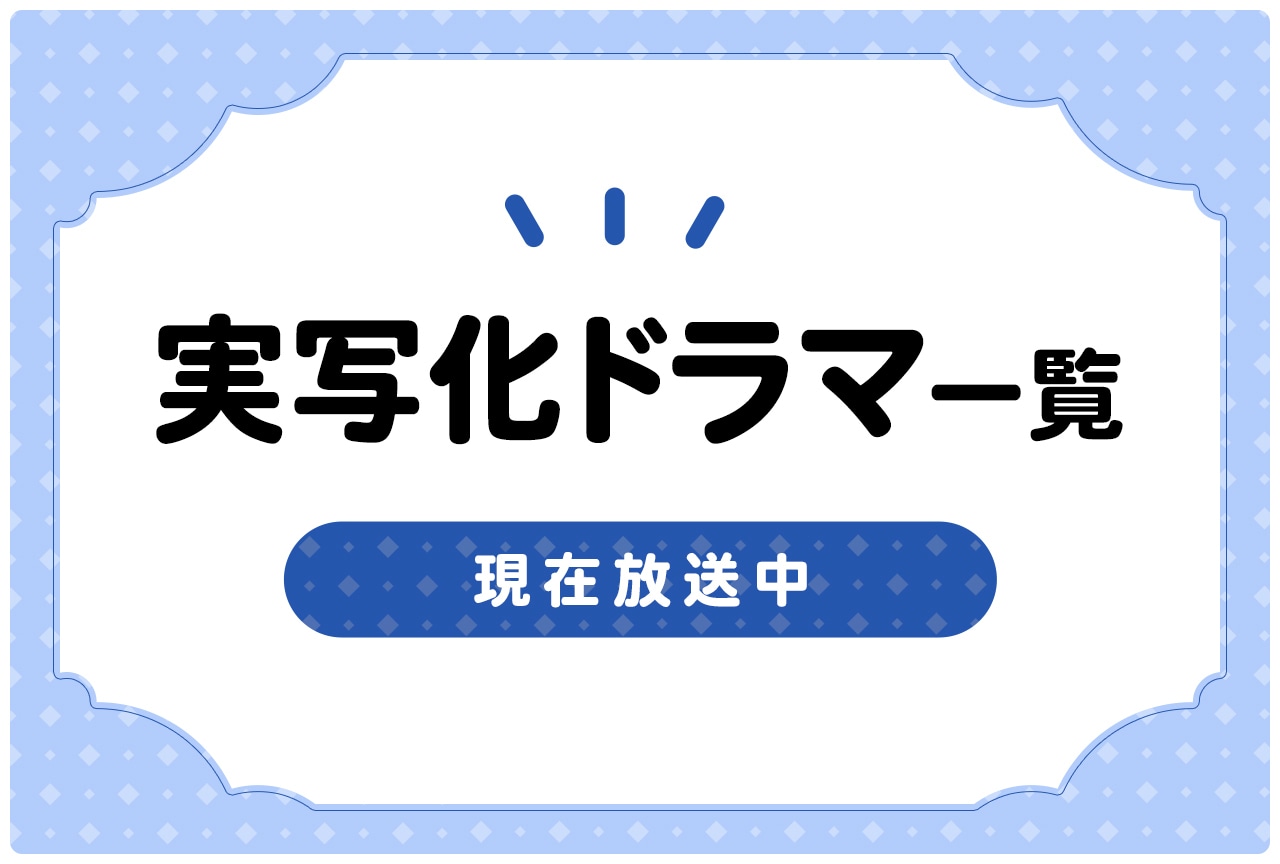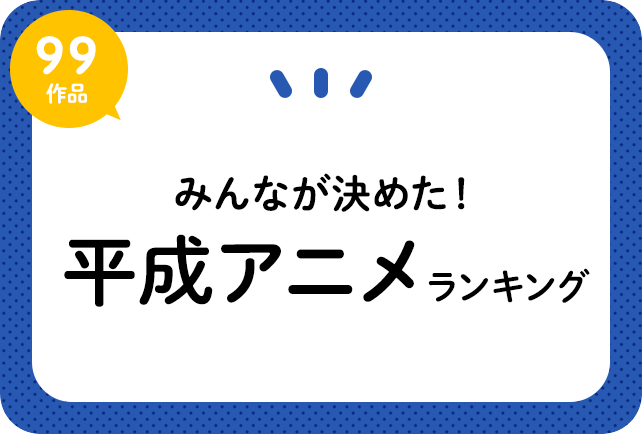「妹という入口を一度閉じて、物語のなかに居場所を求めたという入口から彼女と出会い直しました」──アニメ『違国日記』高代槙生役・沢城みゆきさんインタビュー【連載第1回】
ヤマシタトモコさんによる漫画『違国日記』がTVアニメ化。2026年1月4日よりABCテレビ、TOKYO MX、BS朝日にて放送がスタートします。
本作は、人見知りの小説家・高代槙生が、両親を亡くした姪・田汲朝を勢いで引き取り、同居生活をしていく物語。原作は「マンガ大賞2019」で4位、「このマンガがすごい!2024」のオンナ編で5位に選ばれているほか、実写映画化されたことでも話題になりました。
アニメイトタイムズでは本作の魅力に迫るキャスト・スタッフインタビュー連載を実施! 第1回目は、高代槙生役・沢城みゆきさんにお話を聞きました。
生まれたときから自分がハッキリしているけれど、それでいいという自己肯定感が高いわけではない
──原作・シナリオを読んだときの感想を教えてください
高代槙生役・沢城みゆきさん(以下、沢城):まず、漫画という媒体を最大限に活かしきった作品だと思いました。文学のなかにあるような純度の高いセリフから、日常で私たちも口にするようなセリフも出てきて、それが共存している。純文学っぽい空気を纏いながら、しっかり現代にもつながっているようなストーリーで、とてもレンジが広い作品だと思いました。
絵は、独特な線の細さのなかに、すごく筋力を感じて。繊細に見えるのに力強い絵でまとまっているんです。一人の役者・原作ファンとしては「これは人間の肉声を受け付けない、きっと乗らない作品だろう」という空気感をそこはかとなく感じながらも、でも参加したい気持ちもあって……という、複雑な気持ちでした。
──そんな本作で、沢城さんは高代槙生を演じます。演じるなかで槙生をどういうキャラクターだと感じていますか?
沢城:とてもハッキリと物を言うけれど、相手のことを否定して喋ったり、自分のなかでの正解を誰かに押し付けたりはしない人。生まれたときから自分がハッキリしているけれど、それでいいという自己肯定感が高いわけではなくて。社会に出てから自分ができないことがたくさんあることも自覚していて、それと対峙する苦しみを抱えている人だと思っています。
彼女の言葉は、何だか聖人君主のような物言いに聞こえるかもしれませんが、全然そんなことはなくて。彼女の中にも言語化できない気持ちがたゆたっているとも感じています。
──彼女の言葉選びに心が動かされるときがあります。「アサガオの観察日記なんて大人になってからやったほうが楽しいに決まっている」という言葉が、個人的にはすごく腑に落ちました。
沢城:その言葉も押し付けてはいないんですよね。「アサガオの観察日記は大人になってからやったほうが楽しいに決まっている(と私は思っている)」なんだと思います。
第1話のなかに「乾いた寿司は食べるに値しない。本物の寿司を食べるぞ」という、原作にはないセリフがあるんです。あのシーン、最初は「本物の寿司を“食べさせてやる”」だったんですよ。ただ、槙生は誰かに何かを押し付ける言い方はしないと思ったので、「ここ、本質の部分に抵触していて言いづらいかも……」と監督に相談したんです。それで「食べるぞ」になりました。
──細かい部分ではありますが、セリフの語尾などひとつでその人物の伝わり方が変わる、と。
沢城:自分がいいと思っているものを決して押し付けはしない。槙生は誰も否定しないんですよね。ただ、これを肉声で表現するとなるとすごくハードルが高くて。書き言葉だけができる最大のメリットを生かしたセリフがたくさんあるので、大変でした。
──先ほどおっしゃっていた「漫画という媒体を最大限に活かしきった作品」というところにつながるお話ですね。
沢城:そうですね。アニメ化するのは本当にチャレンジングだと思いました。
演じるうえで共感はあまり必要なくて。最終的には“同感”することが必要なのかなと
──お話を聞いていると、沢城さんは槙生をとても理解して演じられたのかなと思いました。
沢城:それがですね……私は、彼女の姉で朝の母親である実里の気持ちのほうが分かるんです。作中では、槙生や朝から見た実里がたくさん書かれていましたが、私自身は描かれていない部分の実里の本体をかなり知覚できている自信があります。
──槙生は姉の実里が嫌いだったと、第1話から言っていました。
沢城:そうなんです。実里と友達になれるというのとはちょっと違いますが、同じお姉ちゃんという点で言えば、かなり彼女の味方になれるなと思いました。
そう感じながら原作を読んでいると、どんどん槙生から心が離れてしまって、困りました(苦笑)。ですので、妹という入口を一度閉じて、物語のなかに居場所を求めたという共通点から彼女と出会い直しました。
私もどちらかというと、外で友達と遊ぶよりひとりで図書室にいる時間が長かったですし、物語のなかにいるほうが心地よいというタイプなんです。何なら中学生からこの仕事をやらせていただくようになってからずっと物語の中を必死に生きてきて、30歳で報道番組のナレーションをやるまでリアルな国のことはほとんど知らなかったくらい(笑)。
──パーソナルな部分で寄り添える、共感できる部分を探していた。
沢城:そうですね。槙生と共有できるものを探していたら、「物語のなかに居場所を求めた」というところを見つけました。
──キャラクターに共感できるかどうか、という点は演じるうえで大切になってくるのでしょうか。
沢城:これは私個人の考えですが、共感はあまり必要なくて。最終的には“同感”することが必要かなと思っています。好きとか、思いを寄せられる・寄せられないという部分は超えていくというか。彼女が摂取しているエアロゾルを感じていくという感じでしょうか……。
例えば、本作で言えば、槙生が朝という存在を肌でどう感じていくのかとか、笠町(信吾)くんをどのレベルまで自分のなかに入れていくかとか、醍醐(奈々)やコトコといった友人をどのあたたかさで心のなかに置いておくのか、とか。
恐らく彼女がいちばん難航しているのは「過去形」と言い切っている姉の存在が、自分のバックグランドにあり続けていることを知覚できていないということ。そういう彼女の世界のなかに存在している人たち・思いを五感でどこに置いていくかを、丁寧にやり切れたらいいなと思って演じていました。
──共感するのではなく、相手との距離感などを感じるといいますか。
沢城:そうですね。本作は魔物を倒すとか世界を救うとかとは違う、かなりリアルに近い物語が描かれています。だからこそ、我々も同感しながらリアルな感覚でいないと成り立たないんですよね。
だからと言って、キャラクターは自分とは違う。例えば「朝」と呼び止めるときのセリフですが、私自身は母親でいる時間が長くなっていることもあり、「朝」の呼び止め方に気を付けないと「母親」としての制止のコールになっちゃうんですよ。槙生はそうじゃなくて、「朝」と言ったときには、このオーダーが通っても通らなくてもいいと思っている。そういう人なんですよね。
──意識していないと、自分自身のパーソナルな部分がどうしても出てしまう。
沢城:そうなってしまうかもしれないのが怖いですね。だから、相当切り離して、設定を入れ直しました。母親と娘という関係に似ているけれど、似て非なるものであるというのが本作のいちばんのうま味なので「母親にならないように」というエマージェンシーをずっと自分のなかで鳴らしていました。