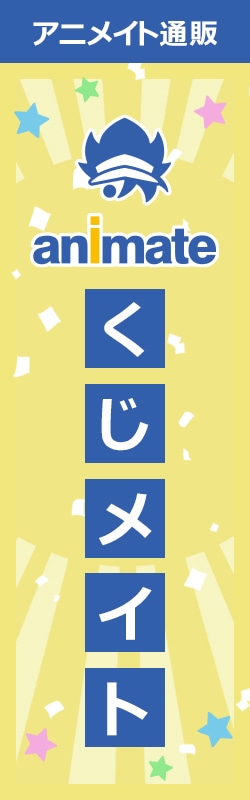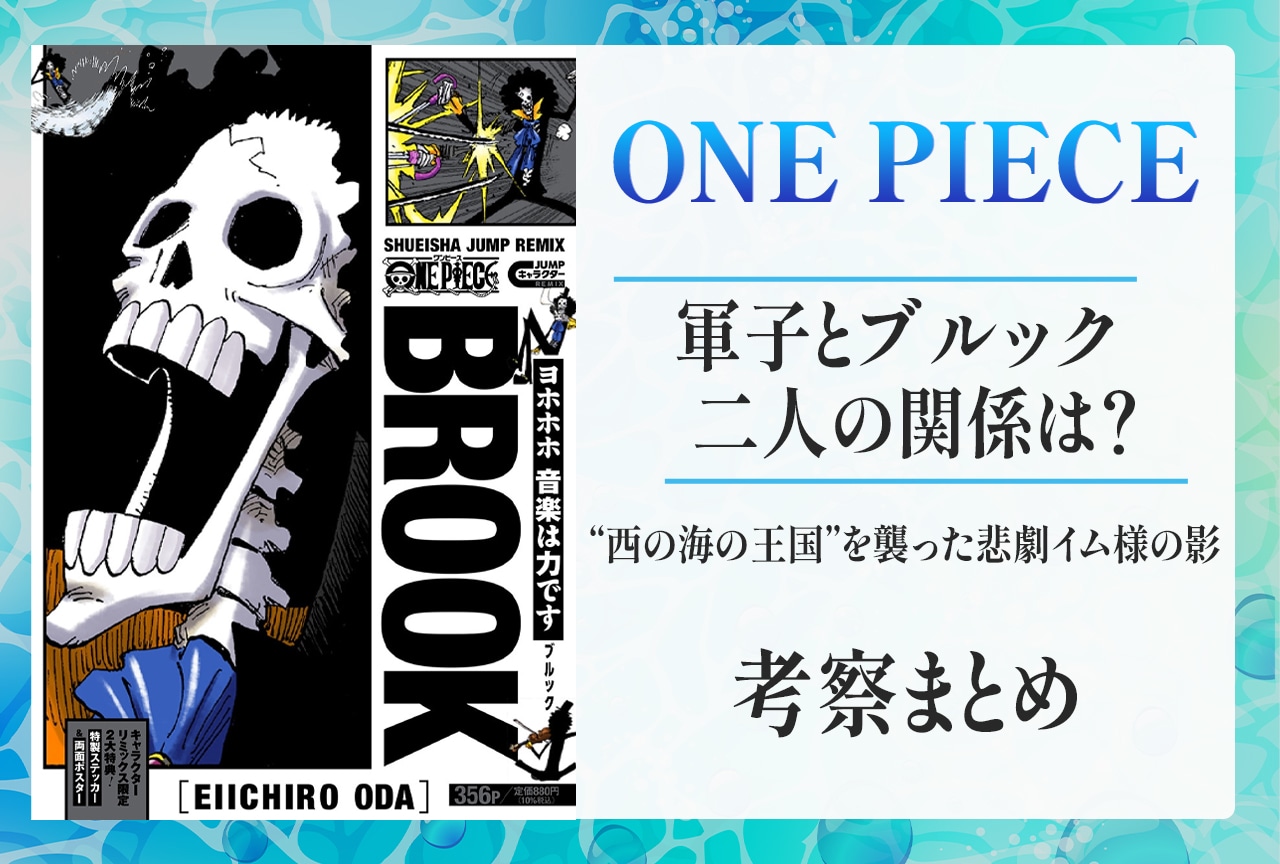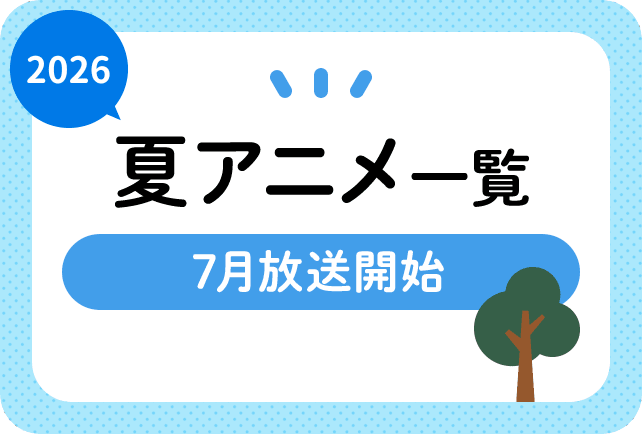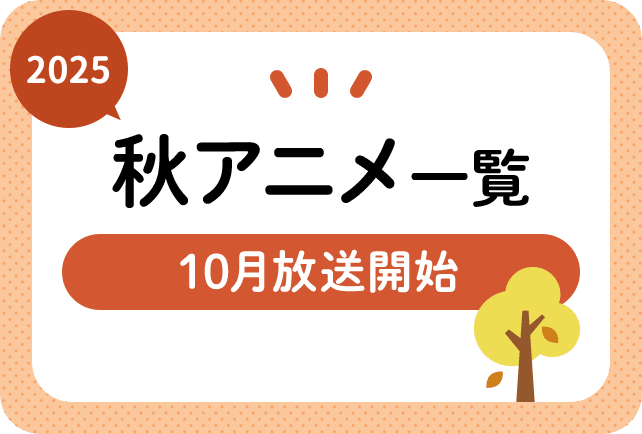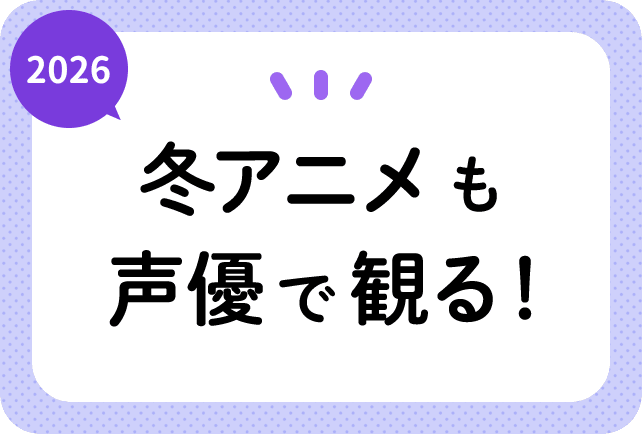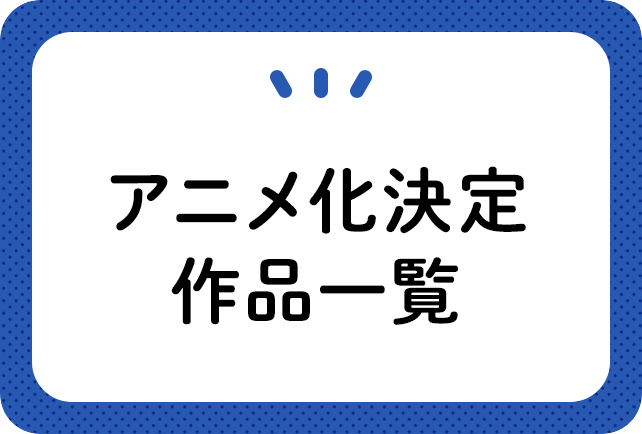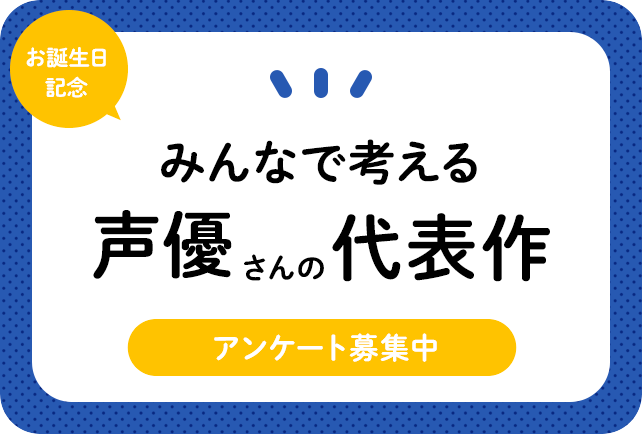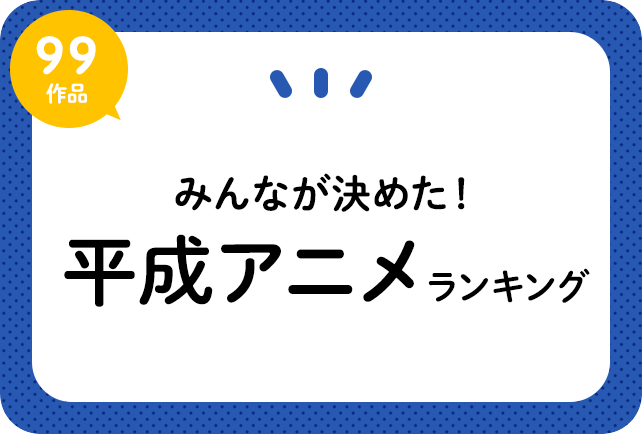冬アニメ『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-』 ソロン役・小笠原仁さん×シオン役・土岐隼一さんインタビュー|ここからどんどん物語が加速していき“クリス”が何者なのか明かされていきます――
世界的人気を博すグローバルグループ・ENHYPENとコラボした7人の少年たちを主人公に、名門学校デセリスアカデミーで出会った転校生の少女との運命的な物語を描き、世界累計閲覧数2億ビューを記録した大ヒットウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』。本作のTVアニメが2026年1月より放送中です。
この度、5話放送前にアニメイトタイムズではソロン役・小笠原仁さん&シオン役・土岐隼一さんにインタビューをしました。本作ならではの世界観や演じられるキャラクターについて深掘りしていきます。
気心の知れたメンバーだからこそ作り出せた空気感
──最初に、『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-』へのご出演が決定した際のご感想と、原作や台本をご覧になった感想をあわせてお聞かせいただければと思います。
ソロン役・小笠原仁さん(以下、小笠原):ENHYPENさんとコラボレーションしたウェブトゥーンのアニメというところで、オーディションを受けた段階から、「これはどういう温度感で愛されている作品なんだろう?」というのを、僕自身もいちオタクとして考えていました。
なかなかないメディアミックスのされ方なので、もし関われたらそういう空気感を肌で感じられたらいいなと思っていたところで役をいただけて、「これはすごくいい機会に恵まれたかもしれないな」という、そういった方面の期待感がありましたね。
シオン役・土岐隼一さん(以下、土岐):おがじんってENHYPENさんに限らず、韓国の俳優さんやアーティストの方々を知っていたりはすると思うの。その方々を応援したり、いわゆる推していたりしてた?
小笠原:ENHYPENさんの楽曲も聴いたりはしていました。土岐さんはいかがですか?
土岐:周りの演者の方々は最近、男性・女性関係なく韓国の役者さんを好きな人がすごく多くて、自然と名前は知っていました。パフォーマンスがすごいなとか、俳優さんとして、アーティストとしてすごいなとは思っていたんですけど、アーティストとコラボしたウェブトゥーンがあるということは知らなかったんですよね。
その方たちを元にキャラクターを作っているけれど、キャラクター名は違うじゃないですか。オーディションの時に、「どこをゴールにすればいいんだろう?」とは考えました。演者さんの声を当てはめた方がいいのか、それとも作品としての世界観基準でヴァンパイアと人狼という王道のファンタジーコンテンツとして考えた方がいいのか。考えた末に、これは素直に「このキャラクターから出てきそうな声」をイメージして声を作った方がいいのかな、というのは最初のオーディションの段階で考えていましたね。
最終的に、「シオンからはこういう声が出そうだな」と思って演じたところ、役をいただくことができました。だから決まった時に、この『DARK MOON』という作品の空気感を出せる人たち(役者)が集められているんだろうなと感じました。
全員で一堂に会した時の申し送りでも、キャラクターに合っていて、かつコラボ元になったアーティストの方々の空気感、例えばシオンなら明るい方がモデルなのですが、「イメージが近い方たちをキャスティングしました」とおっしゃっていたんです。芝居の方向性と人間性、その総合的な部分で選ばれたんだろうなと感じました。だから、「のびのびやろう」と思えました。
小笠原:最初にそう言っていただけたことで、現場でお芝居するにあたっても「自由でいいんだ」と思えて、すごくありがたかったですね。
土岐:もちろん芝居の微調整はありますけど、大きく方向性が変わった人はいなかったので、みんな結構のびのびやれていたんじゃないかなと思います。
──「12年制の学校」という設定がちょっと珍しいなと思ったのですが、この作品の世界観については、どのように感じられましたか?
小笠原:日本で言うと、エスカレーター式の小中高一貫校に近い感覚だと思うんですけど、ただ「小学○年生」「中学○年生」「高校○年生」みたいな区切りがなくて、一律に12年制という。また、学園が舞台でラブロマンス的な要素がありつつ、登場人物たちはスーパーパワーを持っていて、ヴァンパイアや人狼がいて、さらに主人公を取り巻くさまざまなヒューマンドラマが描かれている。ラブファンタジーとしては王道の設定だと思うんですけど、あれだけ個性あふれるキャラクターたちを一堂に会させて、物語を円滑に進めている原作を先に読ませていただいたときに、「面白い話の作り方だな」と感じました。
土岐:(頷く)。
──キャラクターに声を当てる際、どのようにキャラクター性を考えながらお芝居をされていかれたのでしょうか?
土岐:オーディションのときは、正直どうしようかなと考えていました。ただ、監督のお話の中で「一番イメージに合った方たちを選んでいる」というお話をいただいていたので、少なくとも日常シーン、リラックスしている場面については、「もし自分がシオンだったら、どう感じるだろう?」という直感を大事にして持っていけば、大きく外すことはないだろうなと思っていました。
なので、「ここはこう演じよう」と作り込みすぎる必要はなかったな、という印象ですね。シオンはしっかり考えている子ではあるんですけど、同時に直感で動くタイプでもあるので、その場その場で思いついたことをポンと言っちゃう感じが、僕自身とも重なる部分があったりもしますし、好奇心旺盛なところも含めて、シンパシーを感じる部分は結構ありました。
なので日常的なシーンに関しては、無理なく演じられたかなと思います。ただ、やっぱりファンタジー作品なので、シオンたちが抱えている少し暗い部分と向き合う場面が出てきたときには、「彼の陽気さはどうなるんだろう?」というところは考えましたね。
1話から4話あたりでは、まだその割合は大きくないですが、シオンは空気を読まない子ではあるんですけど読めない子ではないので、そういうときに周りのみんなのお芝居と合わせながら、「シリアスな展開のときは、どう演じていこうかな」というのを、その場で探っていった感覚が強いです。「こうやろう」「ああやろう」と事前に決め込むよりも、その場でみんなと一緒に空気を作っていく方が、絶対に楽しいと思っていました。小笠原くんをはじめ、インタビューを受けているメンバーも含めて、ずっと一緒にやってきた、いわば気心の知れたメンバーでもあるので。
実際、アフレコはめちゃくちゃ楽しかったです。
小笠原:部室みたいな(笑)。『DARK MOON』という作品において、その空気感が、そのままお芝居にもいい影響を与えていた気がします。
土岐:みんなが居心地の良い収録だったんじゃないかな。
──清水さんは皆さんとは初対面でしたよね。
土岐:清水くんは、多分みんなの中で一番「初めまして」の状態でしたし、がっつり掛け合いをする現場自体が初めてだったと思うんです。「こういうセオリーがあるんだ」ということを、現場で初めて知ることも多かったんじゃないかな。
マイクの位置とか、収録の仕方など、どう立ち回ればいいのか、とか。そういうことを周りを見ながら、このメンバーの中で吸収していたんじゃないかなと思います。このメンバーだったからこそ、一番のびのびできたんじゃないかなとも感じています。
平均すると30代前後の現場で、僕と宗悟がほぼ最年長という状況だったので、世代が近かったことも、すごくいい方向に作用していたんじゃないかなと思いますね。
小笠原:清水くんは、それこそ今放送されている4話くらいまで、常にアンテナを張り巡らせて、「次はどうするんだっけ?」と考えながら収録に臨んでいる姿が印象的でした。その初々しさと真剣な眼差しが、かっこいいなと思う瞬間もあって、良い体験だったなと思います。
──話が少し戻ってしまうのですが、小笠原さんがソロンを演じる際に、意識されていることをお伺いできればと思います。
小笠原:この作品のオーディションを受けさせていただいた時は、キャラクターの多い作品ということもあって、複数のキャラクターで受けさせていただいたんですけど、結果的にソロンに決まって。その時に自分の中で一番「なるほど」と思ったのは、キャラや声を変えずに、自分のパーソナルのど真ん中で勝負しようとしたのがソロンだったなという点でした。
そのままソロンに決まったので、「ああ、なるほど。であれば、自分の地続きにあるナチュラル寄りの部分を求めてくださっているのかな」と思ったんですよね。ただ、それはあくまでオーディション時点での話で、実際に他のキャストさんを知って、現場に行って、皆さんのお芝居やキャラクター同士の掛け合いが始まった時に、自分のお芝居的な立ち位置やキャラクターとしての立ち位置、そういったものが全部マリアージュされたときに、役割が明確に生まれてくるんだろうな、という感覚がありました。
実際にアフレコ本番をやってみたら、ソロンというキャラクターのフィルターを通して、自分が心のままにリアクションしていけば、このわちゃわちゃした空気感の中で、いいお芝居体験、掛け合い体験が組み上がっていきそうだなと思えて。だから個人的には、本当にのびのびとやらせていただけたな、という実感があります。
ただ、さっき土岐さんもおっしゃっていたように、ファンタジー作品ではあるので、たとえばバトルシーンだったり、日常とはかけ離れたマインドになる瞬間もあるんですよね。そういうナチュラルではないアプローチが必要になった時に、ファンタジーの世界観には寄り添いながらも、日常の延長線上として演じていたり。
ソロンたちヴァンパイアのみんなは、自分たちの宿命と向き合い、悩みながらも、それがもう当たり前になっていて、そのファンタジーの側面すらも、彼らにとっては日常なんですよね。だから、日常パートとファンタジーパートを意識してセパレートしないように、どれだけナチュラルさを残しながら全編を通して演じられるかというところにチャレンジしていたなと記憶しています。