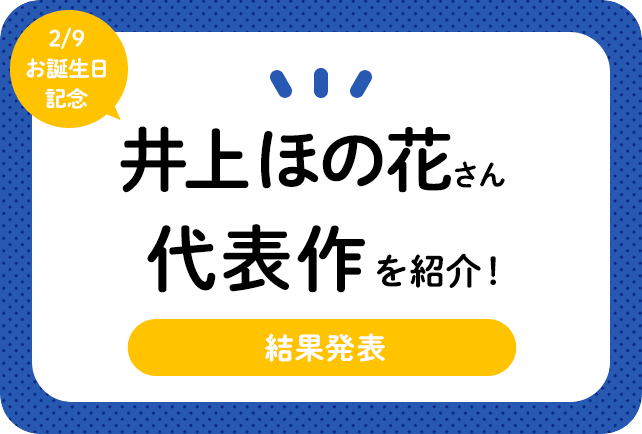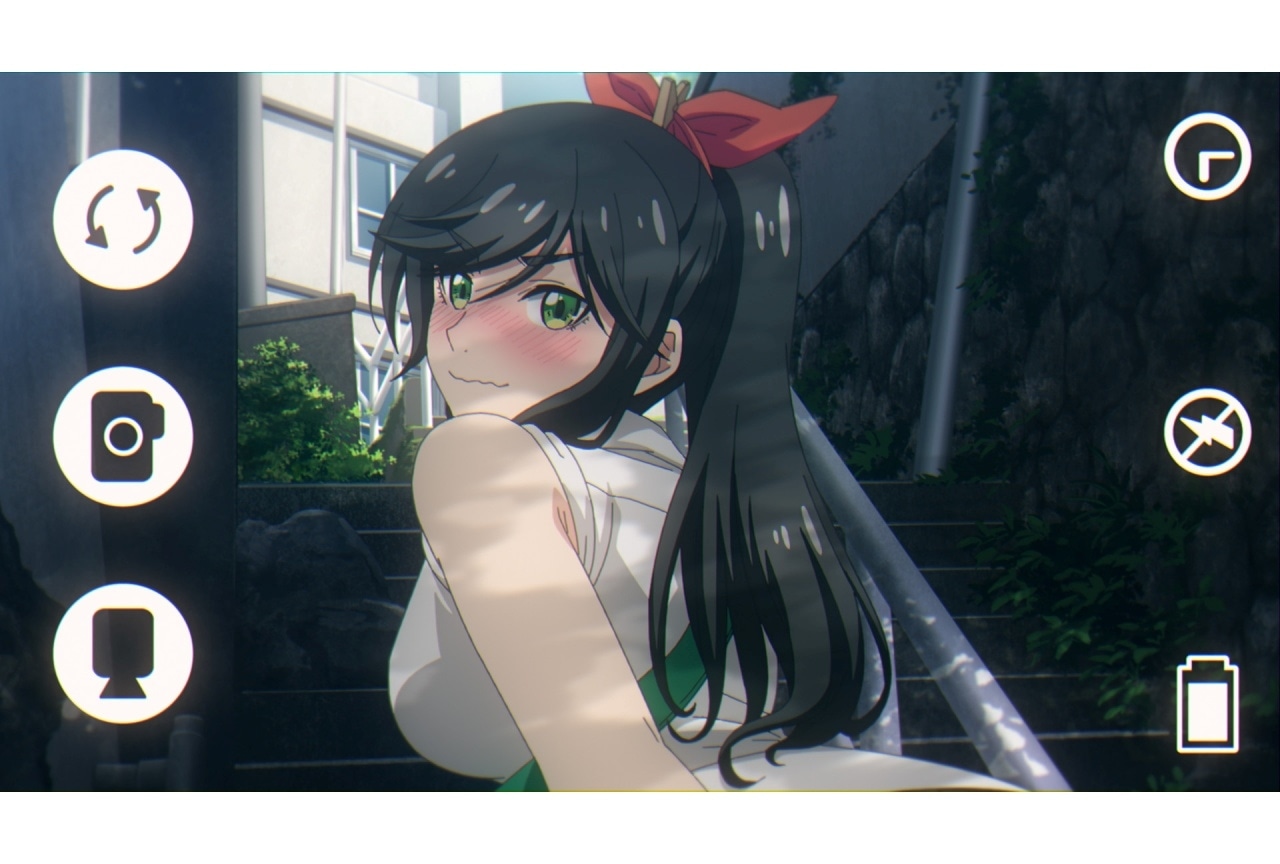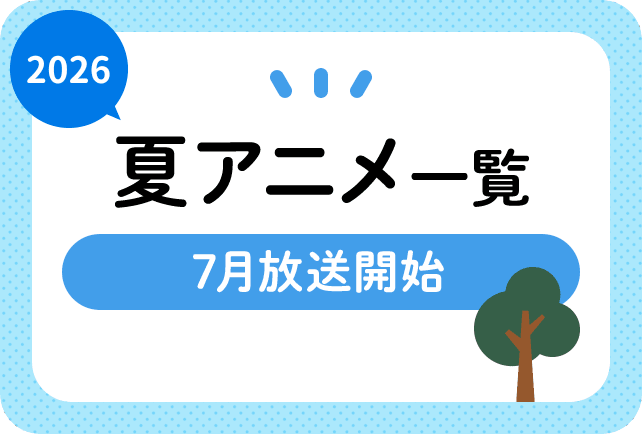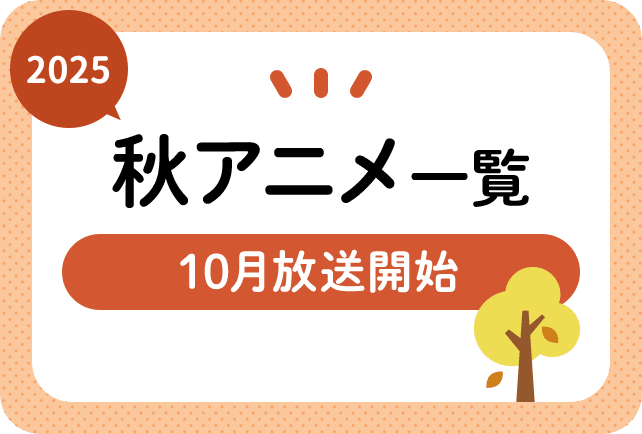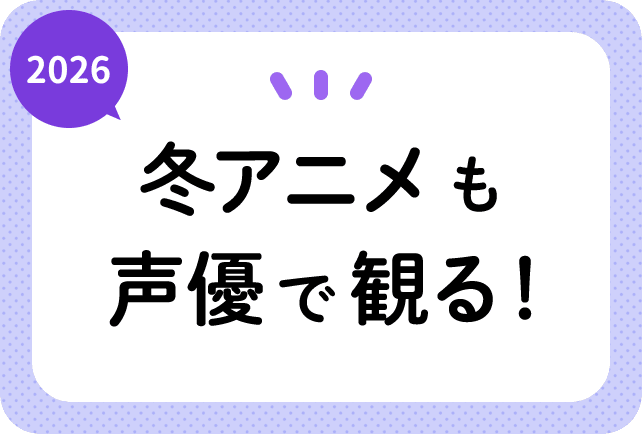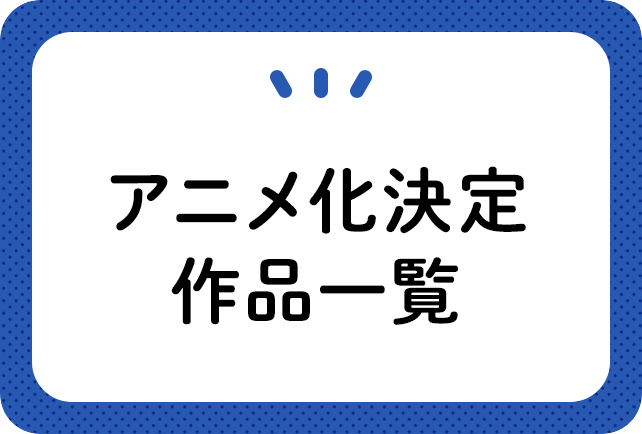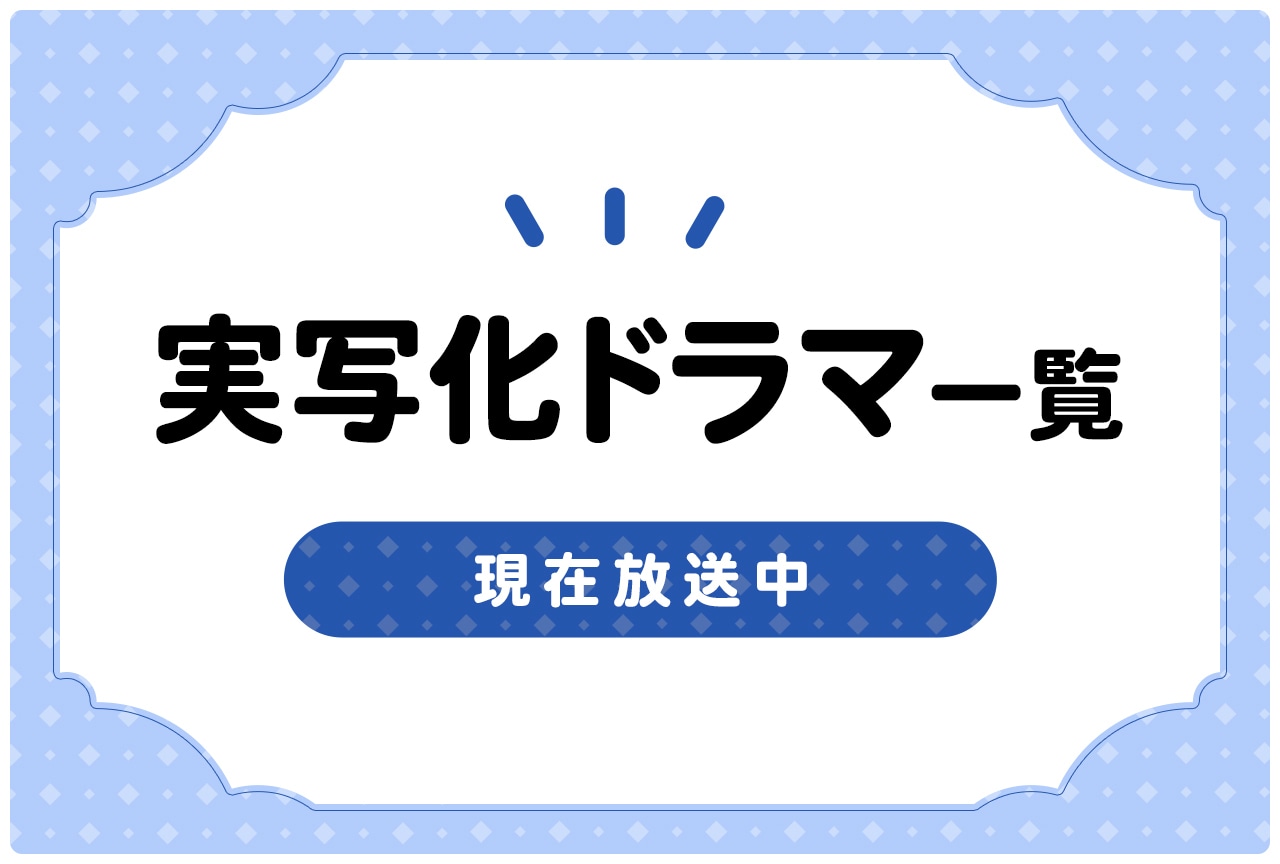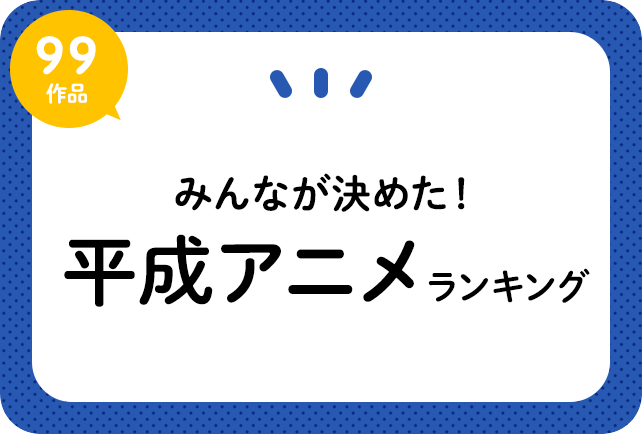『Tokyo 7th シスターズ』茂木伸太郎総監督インタビュー|“真正面から愛を描いた0.7”“未来に恋する5.0”はどうやって生まれた? そして今後の展開、長編アニメ化など語る。
一人の人間が、愛を知る物語
――続いて、『0.7』についてのお話を伺いたいと思います。
茂木:『0.7』は一言でいえば、「一人の人間が、愛を知る物語」です。自分ではそう呼んでいました。これは脚本制作、音楽発注、イラスト制作のすべてにおいて最初から言ってるテーマみたいなもので、結果そうなっていればいいなと思っています。
もちろん物語としてはそれだけではなく、セブンスシスターズという伝説と呼ばれる人たちが実際にはどういう人たちで、どういう壁にぶち当たって、どのように「自分の人生」と向き合ったのか? だったり、これまでの全エピソードに関連する伏線の答えを解き明かす物語ではありました。
プレイしていただけましたか?
――もちろんです!(笑)
茂木:ありがとうございます。どうでしたか?
――個人的な感想にはなるんですが、伝説だと言われている彼女たちの歳相応の面が垣間見えたり、伝説と呼ばれるだけの過去の重さが描かれたりと読み応え抜群でした。なにより最後、全員でライブをやるという彼女たちの選択は心に響きました。それに、おばあちゃんの話は心にきましたね。
茂木:ありがとうございます。ミトの祖母であるイトの人生をどう描くかというのは難しい問題でした。これまでもその存在は明らかにしていましたが、人物としては初登場となるので。しかし、あまり尺をとっても違うなと。イメージ的には『0.7』は90分の映画だったんですよ。扱うテーマ的に尺はそれ以上いらないと思ったし、短いからこそより鮮明に伝わることもある。だからやるべき内容はかなり絞りました。実際には2時間超えになっちゃいましたけど。
――イトの喫煙シーンはとても印象的でした。
茂木:あれも意図的ですね。スタッフから「このご時世的に吸わせていいんですか?」みたいな話も出ましたが、アプリという媒体ということもあってやることにしました。
実際に僕の祖母が、ああやってタバコを吸っていたんです。夜中にひとり、台所で。普段はタバコなんか似合わない素朴で優しい人だったんですが。でもだからこそ、その姿を見たとき、子ども心に彼女の人生を感じました。おいそれと触れちゃいけないし、語れないものというか。もう随分前に亡くなったんですが、そこも人間を描くという部分かと思います。
そういう意味で、そのシーン含め、相も変わらず人間というものを描こうとしました。セブンスシスターズも伝説と呼ばれているけど、本当は僕らと同じただの人間で、だからこそ、あの決断の果てに全員で涙を隠してライブをやった彼女たちの美しさがわかるというか。
――円陣のシーンは『4.0』との対比もあり、涙なしには見れませんでした。
茂木:あの6人の姿は6年前から頭の中で描いていました。ニコは大切な人、つまりミトとイトの望みを叶えるために、愛のために手を掴み、しかし愛のために耐え切れず放してしまう。それを見たミトは、ライブに出る覚悟を決め、空に行き場のない想いを絶叫する。そういう「この世の果て」を描こうとしていました。だからあの円陣シーンの劇伴曲のタイトルは「この世の果て」と言います。
そのあとに待っているものは、降り積もる雪。劇伴曲のタイトルは「降雪 -Theme of Love-」と言います。愛のテーマですね。このシーンも6年前から変わらないイメージを持ち続けていたもので、絵と音楽だけでやろうと決めていました。音楽もピアノだけでいいなと、他には何もいらないなと思っていました。当初からあまりにも強くイメージがあったので、曲については僕からピアノのメロディを岡さん(岡ナオキ氏/劇伴音楽担当)に提出しました。
――絵とピアノだけ。名シーンだったと思います。
茂木:6、7年前……セブンスのキャラデザをしてもらっているくらいの時期だったと思います。何故、あのシーンが頭に浮かんだのかはわかりません。セブンスシスターズという存在を生み出す上で自然と舞い降りてきたもののような気がします。その時点で愛、つまりイトを求めて雪の上を走る6人というストーリーはできていたし、その姿を包む旋律などもあったような気もします。大切な人がもう去なくなってしまったことを知って、ただただ空を見上げることしかできない。圧倒的な孤独感と無力感。人は無力だと思う瞬間と、そして共に無力であることで、一瞬とはいえその孤独さえも包むことができる人間の豊かさを描きたかったんだと思います。なんにせよ、自分で考えたものというよりは、彼女たちから与えられたものだったような気がしています。
――その後は解散への道ですね。予想していたよりも、爽やかで明るかったので嬉しかったです。
茂木:解散を決めて、ニコルがミトに愛について話すシーンで流れる劇伴には「解夏(げげ)」というタイトルをつけました。彼女たちの「夏が明ける」という意味ですね。
「解夏」って仏教用語なんですが、すごく好きな言葉なんです。僧侶さんが90日間の厳しい修行を解く、終えるという意味だそうで。なんでしょうね。役割や責任、誰かの期待、社会という彼女たちを縛っていたものすべてから、夏が終わり自由になる、また自分になるというか。まさに彼女たちにぴったりの言葉だと思ってつけました。
――縛っていたものと言えば、業界のリアルというか、かなり生々しい話もありました。
茂木:「鳥かごのレストラン」とかセブンスと敵対する委員会のことですね(笑)。誤解してほしくないのは、彼らを悪として否定しているわけではないということと、あれは普通のことという点です。
だから、彼らをダメな人間たちとして描いてはいないつもりです。彼らには彼らの正義があるというか、僕が個人的に彼らを悪だとは思っていないことも関係しています。彼らは彼らの立場があって、選択の末にああなっているだけ。ただ、あれは現実世界、社会では普通のこと。普通にいる人たちです。これは社会で働いている大人はみんな知っていることだし、否定も肯定もしていません。『4.0』の最終話で描いた出資者と呼ばれる人たちも、世界観を構築する上で必要だっただけです。
――はい。作りものではないですよね。
茂木:描いたのは、あの状況で、自分の人生や世界とぶつかって、彼女たちが何を言うか、何を選ぶか、それだけです。
――最後に全員でステージに立つこと、そしてそのあと解散することも含め、一貫して彼女たちの人としての「選択」を描いているわけですね。
茂木:そうですね。「なんで解散したの?」「解散する必要あった?」と思う方もいるかと思います。それについては、自分が『ナナシス』で何をやろうとしてきたのか、と言う部分が如実に出ていると思っています。
結果、ステージに立つ者は嘘をつき続けなくてはならないんだと思うんです。嘘というのかな、「笑わない氷の歌姫」という設定があくまで彼女たちの「作った設定」だった、という話をあえて描いたのもそうですけど、彼女たちはアイドルである前に人間です。だから『0.7』ではそんな彼女たちの様々な面を意図的にというか、徹底的に描いています。「最後に涙を隠してステージに立った高潔な彼女たち」「ふざけたノリで設定を作った彼女たち」「実際に活動し始めたら、自分の中で湧き上がる何かを初めて知った彼女たち」「思い描いていたものとかけ離れていく不安と戦う彼女たち」とかですね。
「そうじゃないんだ、アイドルはあれ、ステージの上のあれ、あれが本当の姿なんだ」って言う人がいたら、それはそれですし、これが僕個人の考えというだけです。それでも彼女たち「アイドル」や「アーティスト」を人間として描き、その選択を見届けたときに、彼女たちが「解散」を選んだことに、僕自身は深い共感と納得をしています。あの出来事があって、それぞれが自分の道を行く。一貫して美学の問題かとおもいますが、自分たちで選択し、自分たちでその責任を果たす。その選択をちゃんと背負って前に歩く。本当に素敵な人たちだなと思います。
「愛がテーマ」というのを繰り返し言ってきましたが、もちろん人それぞれ愛の形は違うので、やっぱり違和感がある人もいるとは思います。でもこの物語の結末にミトが気付いたものが、自分としての愛の形なのかなと思っています。愛は手に入れるものでも、成長させるものでもなく、「知る」ものだと。4thライブのときくらいにそう思ったんですよね。というか、元々そういう考え方だったのかもしれません。6年前からエンディングは変わらなかったので。初期プロットに書いてあるとおり、「初夏の空、ミトが歩道橋で振り返るとみんながいて、なにも言わずただ優しい笑顔で手を振っている。夏が明け、氷が溶ける」というラストシーンはずっと頭に浮かんでいました。
――EDで流れるテーマソング「光」の歌詞も、今のお話を表しているような気がします。
茂木:あれも表現は違えど、同じことを伝えたかったんだと思います。でもとにかく『0.7』はこれまでで最も美しいものを描こうとしていました。簡単な仕事ではなかったですが、その後に『5.0』が来ることがわかっていたので頑張れたみたいなところもあります。主題は違えど、『4.0』、『0.7』では共に現実でもがく意味を描いて、やっと「ご褒美」が描けるというか。そんな感じだったので『5.0』は、僕も現場のスタッフもスタート時からなんだか湧いていました。