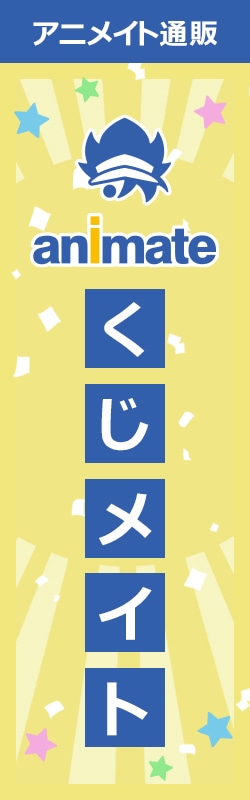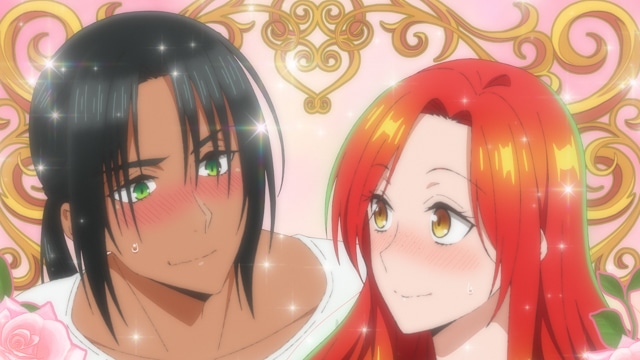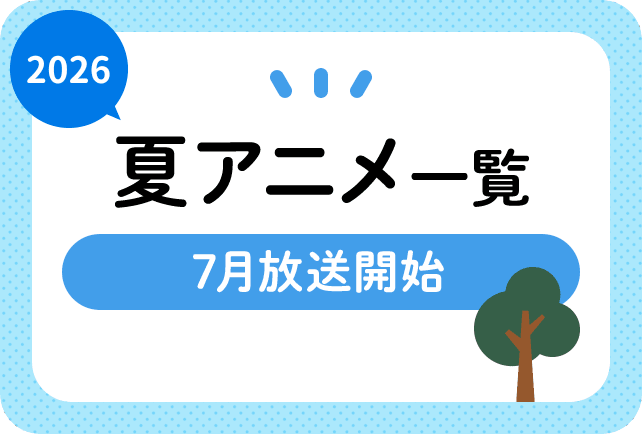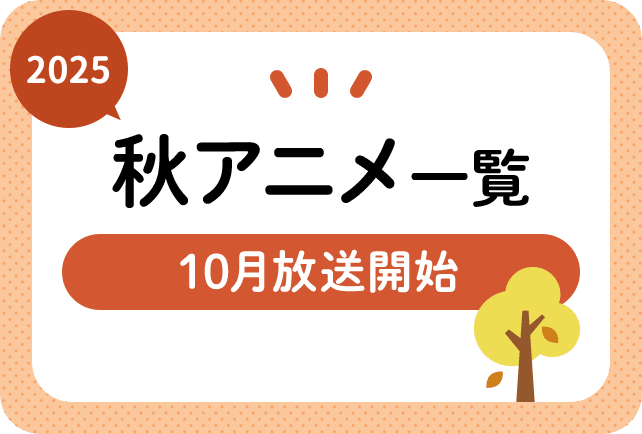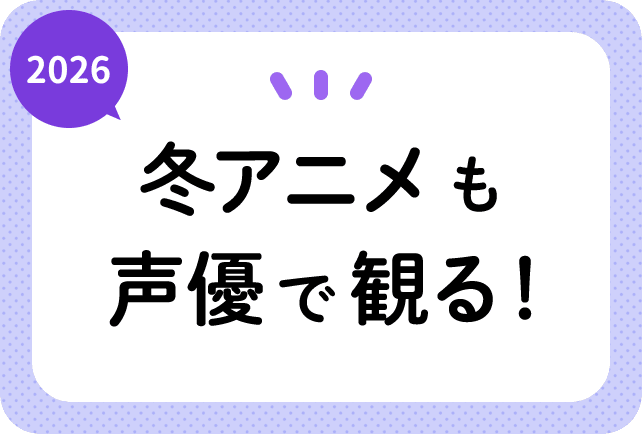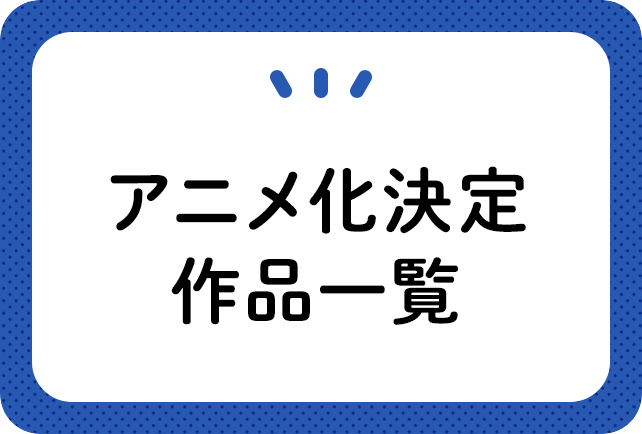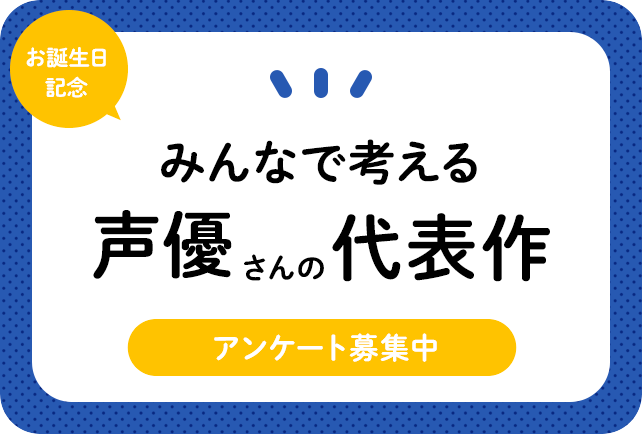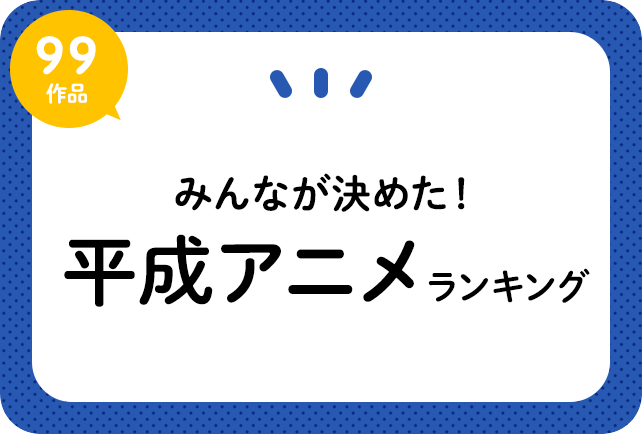マリーと両親の対峙は“復讐”ではなく、自身の“けじめ”として描いた──アニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』リレーインタビュー第6回 監督・北川隆之さん&副監督・砂川正和さん
一周して戻ってきた王道
──では、原作を最初にご覧になったときの印象はいかがでしたか?
北川:小説とコミカライズでそれぞれ面白さが違っているなと感じました。小説はシリアスで重厚な印象が強く、コミカライズはそれを明るく軽やかにアレンジされているんです。シリアスに受け止めることもできるし、コメディにフォーカスすれば軽快で楽しい。切り口によっていかようにもなる面白さがありました。
砂川:僕は、「一周したな」と感じましたね。いわゆる“なろう系”や“悪役令嬢”といったジャンルがひとまわりして、『シンデレラ』に戻ってくるんだなと(笑)。
北川:確かに今はこういう王道が求められているのかという新鮮さがありましたね。
砂川:そうなんですよ。少し前というか、今もそうかもしれませんけど、“異世界転生”ものや“悪役令嬢”ものって、いかに王道を外していくか、“裏”を狙っていくかという部分が目立っていた印象があったんです。
それがド直球のシンデレラ・ストーリーに回帰するのかと。もちろんこの作品にもひねりはありますし、すれ違い要素の面白さはありますが、ベースは『シンデレラ』というのが面白かったです。
──本作をアニメ化するにあたって、どのような部分を大事にしようと考えましたか?
北川:先ほどお話ししたとおり、シリアスさと軽やかさのバランスをいかに取るかという部分ですね。小説、コミカライズともにファンがいらっしゃるので、極力両方のいい部分を拾っていくようにしました。
ただ、“溺愛”という大きなテーマがあるので、それを見せ場とするなら、やはり軽快さや明るさを意識的に入れていくことになるだろうな、と。そのうえで、王道を丁寧にやること。変に奇をてらうのではなく、視聴者に安心して見てもらえるような作品づくりを大事にしました。
砂川:北川さんは、いいと思ったら制限を設けずにそのまま表現していいよと、かなり幅をもたせてくれる人なんです。
今おっしゃった軽快さや明るさも、「アニメだから」といって表現を狭めるのではなく、デフォルメしたり、ワイプを出したりと、コミカライズの演出をそのまま採用するようにしていました。やりたい表現を制限なしにできたと思いますし、結果として作品全体の優しい雰囲気につながったのではないかなと思います。
──たとえばイルザとハンナがミオにぶん投げられるシーンも、シリアスから一転してギャグ調になるという緩急があり、とても面白かったです。
北川:急にテンションが変わるので、最初は不自然にならないか少し不安だったんです。でも、このシーンはコミカライズのテンションが魅力的だったので、素直に参考にさせていただきました。
砂川:コミカライズはギャグ表現の幅が広いので、全体としてもたくさん参考にしています。
──シリーズ構成の猪原健太さんとはどのようなご相談があったのでしょうか?
北川:最初に小説の何巻までやるかを猪原さんたちと決めていきました。第2巻までやるのがちょうどいいだろうということになり、猪原さんがその範囲でシリーズ構成を作ってくださったという流れです。
砂川:猪原さんの構成からそんなに大きな変更もなく、各話のシナリオに移行していきましたよね。
北川:そうですね。あと、これは僕が言ったのか猪原さんがおっしゃったのか覚えていませんが、各話ごとに必ず“ヒキ”を作ることにしたんです。本編自体にサスペンス要素があるので自然とヒキは生まれるのですが、それでも飽きずに見続けていただけるような終わり方を意識するようにしました。
砂川:細かい部分だと、料理や食材などの確認もありましたよね。この作品は現実の歴史をベースにしていることもあり、架空の食べ物を入れられないので、登場する食べ物がその時代に即しているかをちゃんと確認するようにしました。
北川:ミオは焼き鳥を食べていましたけどね(笑)。
──第4話で王国騎士団の砦に行ったときですね。
砂川:あれはコミカライズ通りなんですよ(笑)。そういう現実離れしていても面白い部分は、しっかり見せるようにしました。
──第9話でミオがルイフォンにジャーマンスープレックスをかますところも笑いました。
砂川:あれもコミカライズから採用させていただきました。
北川:最初はもう少し控えめなSEだったのですが、確かダビングの現場で僕か誰かがもっと派手にしちゃおうと(笑)。そういう意味では、ミオやルイフォンはすごく動かしやすかったですね。
エンディングで描いたマリーの生活感
──では、マリーについておふたりはどのように描いていこうと考えましたか?
北川:マリーというキャラクターは不思議な存在で、彼女の魅力をひと言で説明するのは難しいんです。もちろん“いい子”なのは間違いないのですが……。
砂川:難しいキャラクターでしたよね。大貴族の婚約者なのに自分を卑下しているという、ともすれば嫌味に見えてしまうキャラクターなので、どうして自分を卑下するのか、原因となるつらい境遇、生い立ちをはっきり見せる必要がありました。そうでないとただの成功者の物語になってしまうので。
北川:しかも元が美人なので、ネガティブになりすぎると余計に嫌味に見えてしまうんです。だからこそ心根がまっすぐに見えるようにするのが重要で、それをうまく表現してくださったのが、マリー役の本村玲奈さんでした。本村さんの声には嫌味のない透明感があり、まっすぐなマリーにぴったりだったんです。今回、本村さんにお願いできて本当によかったなと思っています。
砂川:それから、マリーはその周囲をどう描くかですよね。マリーは作品の“基準”となるキャラクターなので、特別に何かを強調するよりも、周囲の人物を動かすことを大事にして、自然とマリーという存在が浮かび上がるようにしました。
北川:マリーの描き方でいうと、砂川さんが絵コンテと演出を担当されたエンディングが素晴らしかったです。寝ぐせが爆発したマリーは、僕からは絶対に出てこない(笑)。
砂川:本編でなかなかマリーの生活感を出せなかったので、エンディングで彼女の生活感が見えたらいいなと思ったんです。
北川:マリーのかわいらしさや素直さが出ていました。
砂川:そう、マリーって素直なんですよ。キュロスが惹かれたのもまさにそういう部分。その隠し切れない純粋さにみんな惹かれていくんです。エンディングで表現したかったのも、本人が自覚していない日常の何気ない仕草にこそ輝きがある、ということでした。そのキラキラは、アナスタジアも羨ましく思っていたはずです。
──では、キュロスについてはいかがでしょうか。
北川:彼は正統派のヒーローでありながら、少し抜けたところがあるキャラクターです。お金持ちで完璧なのに、マリーが絡むと急に視野が狭くなってしまう。“かっこいいのに不器用”というギャップが魅力的なので、それをどう映像で表現するかを意識しました。
砂川:原作の時点で、読んでいるこちらが恥ずかしくなるくらいマリーを溺愛しているので、とても描きやすかったです。崩していいイケメンって自然と映像に落とし込めるんです(笑)。
北川:最終話でミオが踊っているふたりを微笑ましく眺めていましたが、我々もまさにミオと同じような視線を向けていました。
──キュロスは決めカットのキラキラした感じもよかったです。
北川:あれはもう定番ですよね。コミカライズでも“花を背負ってキラキラ”みたいなシーンが効果的に入っているので、それも参考にさせていただきました。
砂川:ただ、北川さんってああいったイメージシーンのキラキラを避けがちですよね? 北川さんに限らずですが、過剰なアニメ演出って演出しているほうも恥ずかしくなるんです。いわゆる“ピンクの背景でキラキラ”という演出ですね(笑)。でも、それを笑っちゃうくらい真面目にできたのがこの作品だったのかなと。
──キュロス役の濱野大輝さんがおっしゃっていましたが、決めカットのキュロスはマリー視点の場合が多いから、お芝居もイケメン寄りにしたそうですね。
北川:ええ、「めちゃくちゃイケメンでお願いします」とお伝えしました。濱野さんは、キュロスのかっこいいところとおっちょこちょいなところをしっかり演じ分けてくださって、その演技の振り幅に助けられました。あと、シンプルに声がいい(笑)
一同:(笑)
砂川:濱野さんの声は色気があるんです。ギャグっぽくなっても、マリーを溺愛しても、気持ち悪くならず、どこか色気があって、かつかわいらしい。そのバランスがよかったですね。