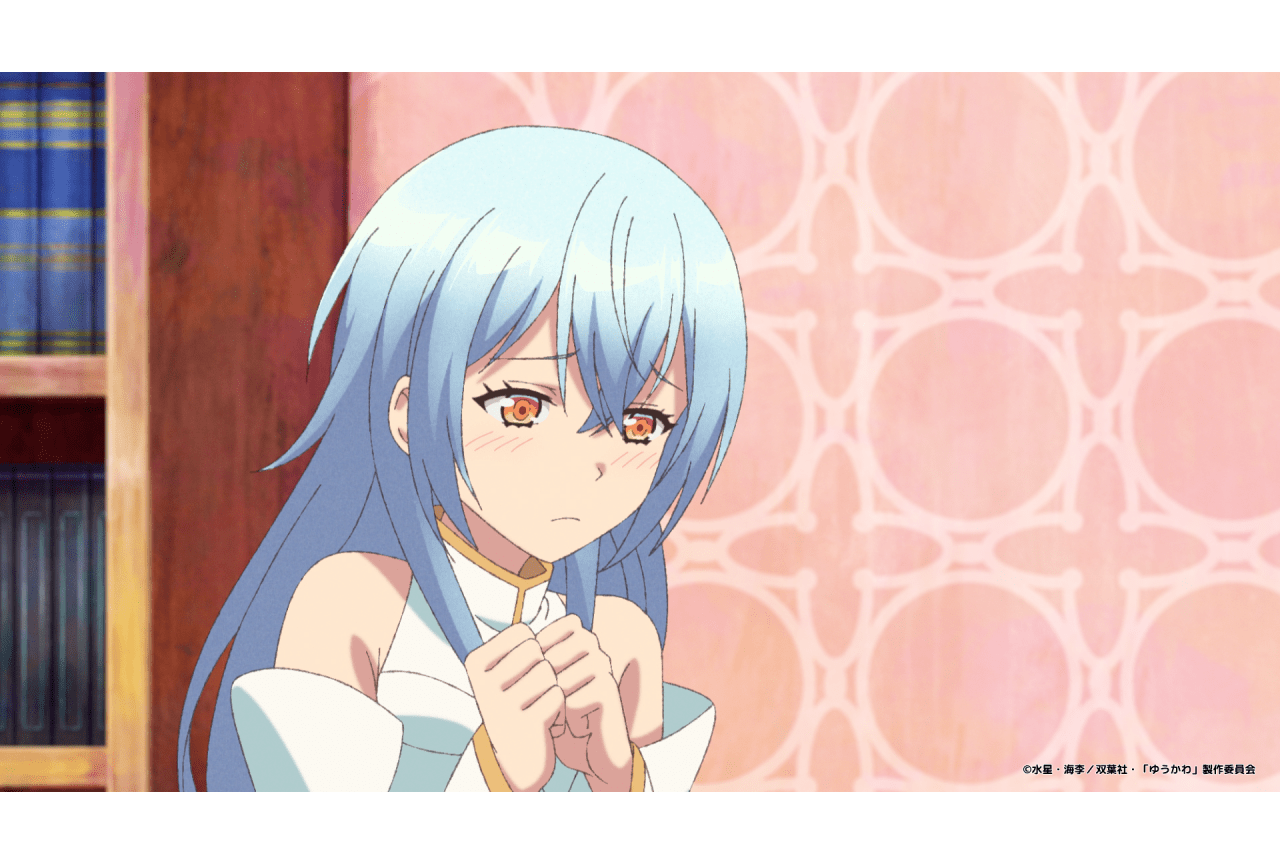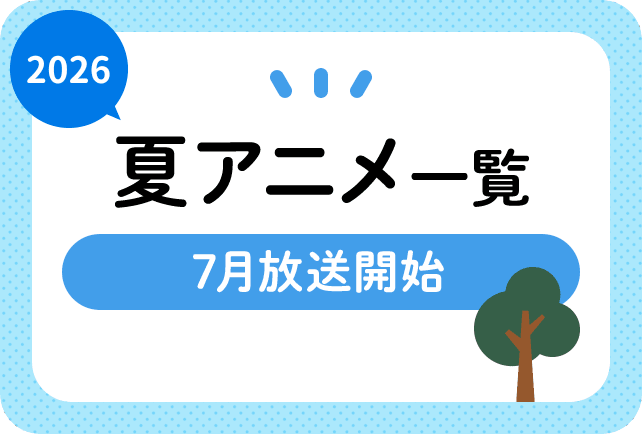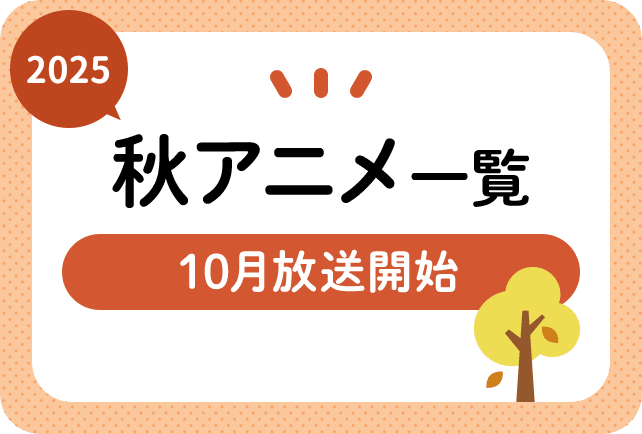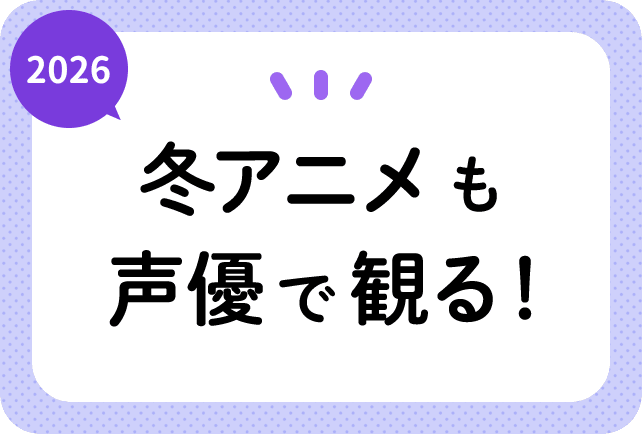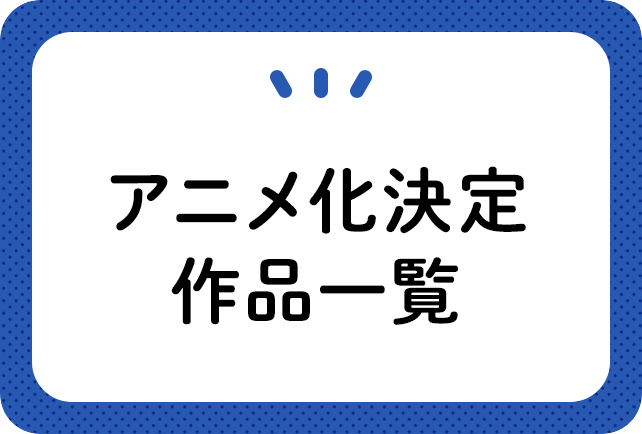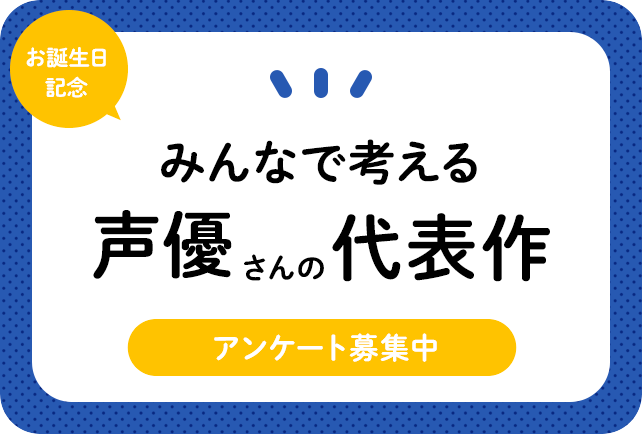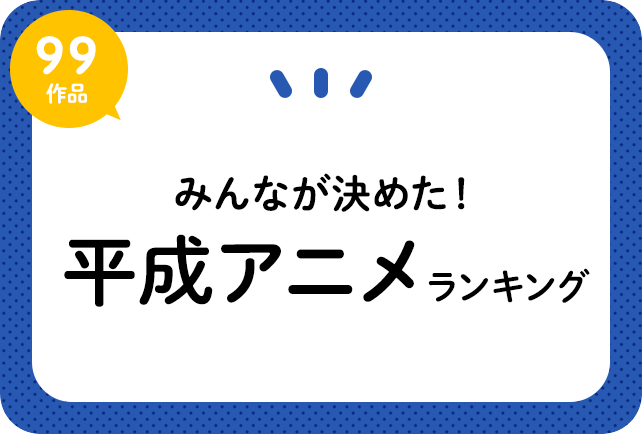イクニプロデュース Reading in the dark『愛の地獄変』総合演出・脚本 幾原邦彦さんインタビュー|体験としての朗読劇、その魅力と挑戦
2024年10月に上映された、イクニプロデュース Reading in the dark『春琴の佐助』。
その第二弾として、イクニプロデュース Reading in the dark『愛の地獄変』が12月4日より上映されます。
今回の上映にあわせて、総合演出・脚本を務める幾原邦彦さんにインタビューを実施しました。
作品の見どころはもちろん、脚本・演出の淡乃晶さんとのタッグ、題材に『地獄変』を選んだ理由、Reading in the darkという形式に込められた意図など、幅広くお話を伺いました。
前作『春琴の佐助』をご覧になった方はもちろん、今回初めてReading in the darkに触れる方にも、ぜひ読んでいただきたい内容となっています。
『Reading in the dark』誕生の背景
──まず、『Reading in the dark』が生まれた背景についてお伺いできればと思います。どのようなコンセプトで立ち上げられたのでしょうか?
幾原邦彦さん(以下、幾原):従来の朗読劇のように、舞台上で役者が本を読み読み上げるだけではなく、観ている―聴いている観客自身が「その物語を体験する」ような作品を作りたいと考えました。
その“体験”を中心に設計するため、体験と音のためにあらゆる要素を削ぎ落として洗練する方向にしました。物語を伝えるのではなく、観客が感情をダイレクトに“体験”することに集中できる形にしていったんです。
観客に物語を伝えて「どういうことだろう?」と考えさせてしまう瞬間があると、それは“体験”から離れてしまう。だからこそ、とにかくジェットコースターのように、乗ったらすごいスピードで最後まで駆け抜ける、そういう作品が良いと思っています。そのためにも、いかに観客に考えさせないかが大事でした。
結果として、削ぎ落したからこそ生まれた聴覚に振り切った体験という、これまで見たことのないような表現が形になりました。一般的に想像する朗読とは、体験も感覚も違うものになったと思います。
『Reading in the dark』というのは、演劇でもあり、朗読でもあり、名前がまだつけられてないようなジャンルなんです。まさに『Reading in the dark』、暗闇へ導かれる行為そのものが独自の体験になっていると感じています。
前作『春琴の佐助』の反響と手応え
──前作『春琴の佐助』の振り返りもお伺いしたいのですが、ずばり手応えはいかがでしたか?
幾原:率直に、良かったですね。初めての試みだったのでどうなるかわからなかったのですが、実際にやってみたら上手くハマりました。観客の方も驚かれたのではと思います。
──ああいうスタイルの朗読劇は、珍しいですよね。
幾原:そうですね、世界的に見てもあまりないと思います。非常にポテンシャルの高い舞台を作れたと感じていますし、自分としても「面白かったな」という思いがあります。
──脚本・演出を担当する淡乃さんとの協働についてもお聞かせください。前作が初タッグだったのでしょうか。
幾原:淡乃さんとは、前作の上演の1年ほど前から「Reading in the dark的なことをやりたい」と話して、意見交換しながら脚本を作っていました。
ある時ふっと『春琴抄』という題材が頭に浮かんで「どうだろうか?」と提案したんです。淡乃さんも「面白い」と言ってくれて、そこから形になっていきました(※1)。
──お互いに刺激を受ける部分や、創作プロセスの違いはありますか?
幾原:シナジーのように、双方の良い部分が出れば良いなと思いながら始めました。実際、淡乃さん単体で作るものと、僕が加わって作るものは、また違うニュアンスになっていると思います。
僕はもともと舞台にも携わっていたので、淡乃さんとは最初から意見交換しやすかったです。もちろん意見の相違はありますが、強烈にぶつかることはありませんでしたね。
※1:淡乃さんの音声作品『イルミラージュ・ソーダ』を幾原さんが聞いた際、音声作品そのものが何かを“体験する”行為になっているのが面白いと思ったのがきっかけ。


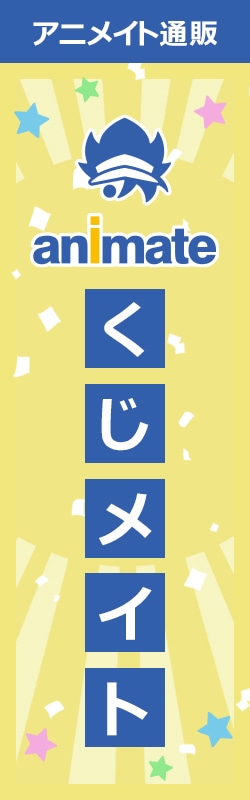






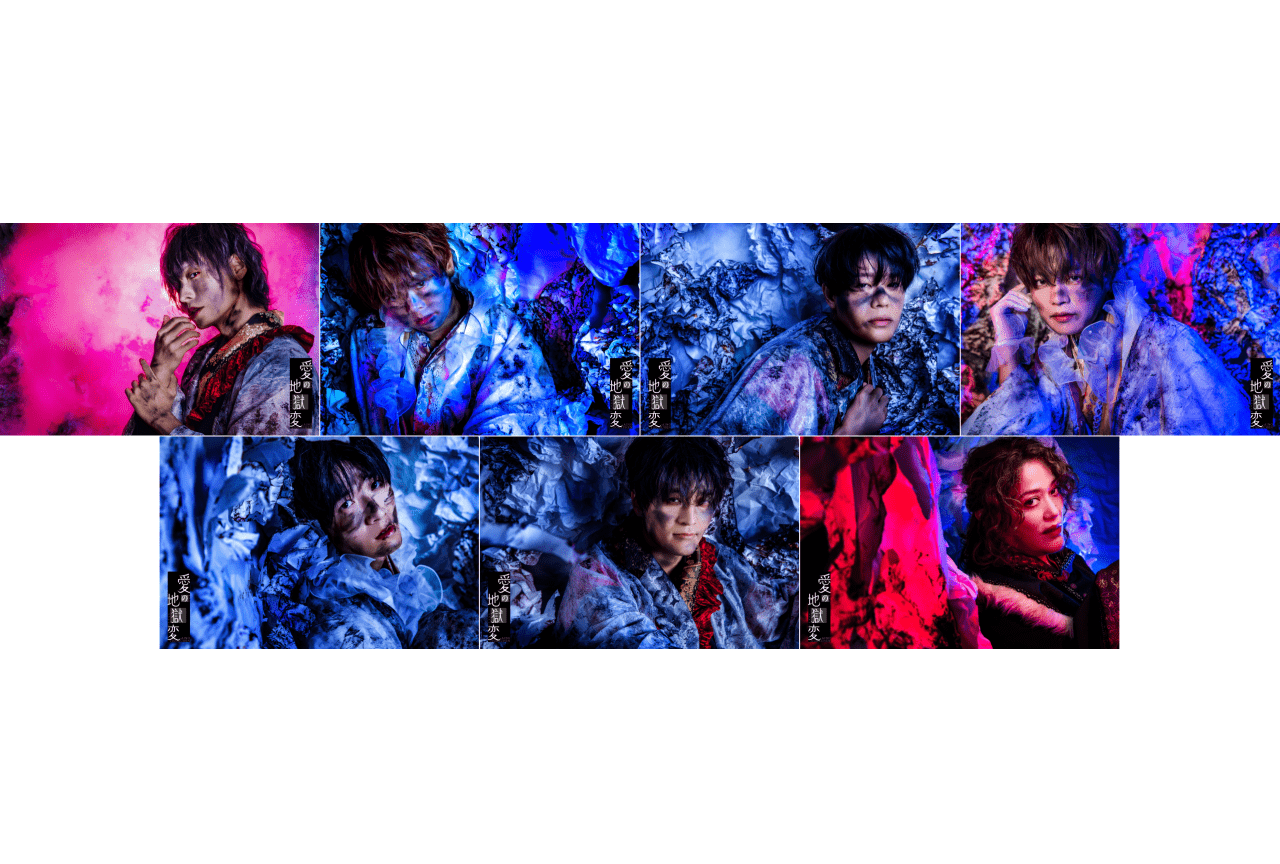


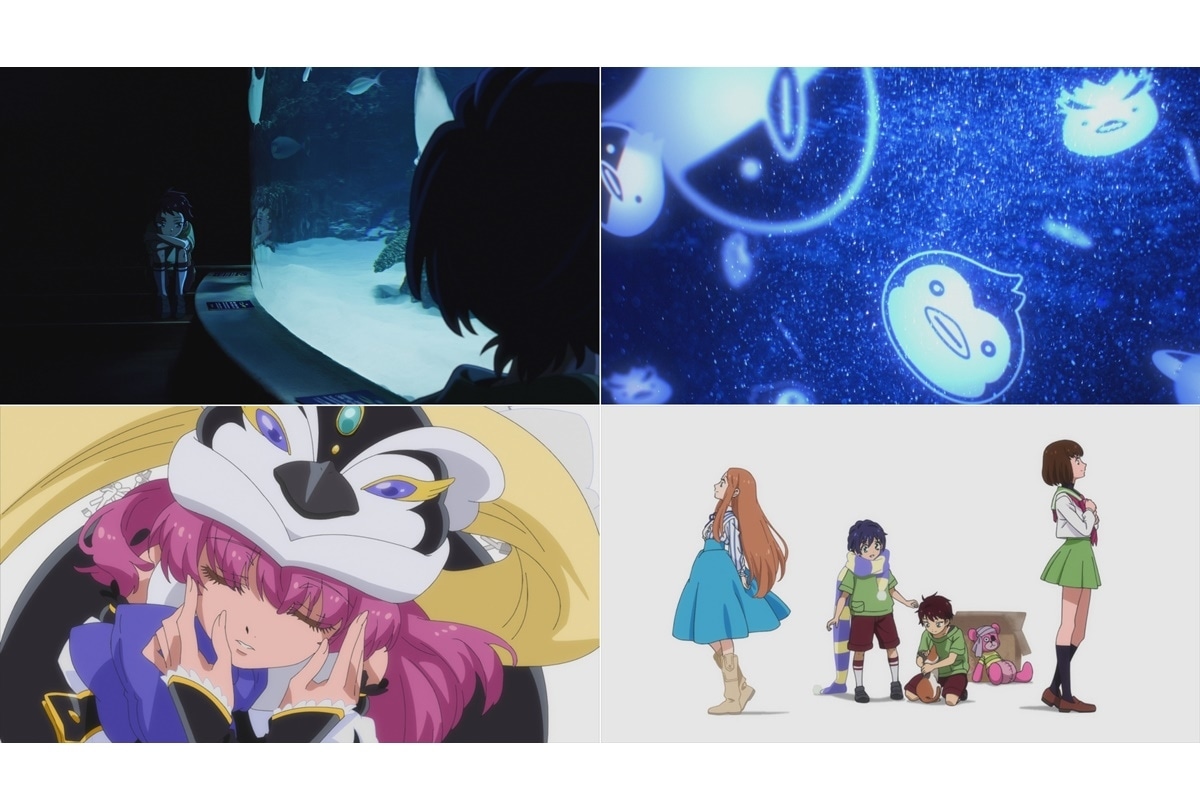










![【ムック】リスアニ!Vol.60 「あんさんぶるスターズ!!」音楽大全[下] コズミック・プロダクション&リズムリンク編 スペシャルCD付き完全数量限定セット【ESバンドによるアレンジが施された貴重なスペシャルCD付き!】の画像](https://tc-animate.techorus-cdn.com/resize_image/resize_image.php?image=01091015_696056acbea21.jpg&width=127&height=127&age_limit=&sex_characteristic=&image_display_restriction=0&warning_restriction=0)