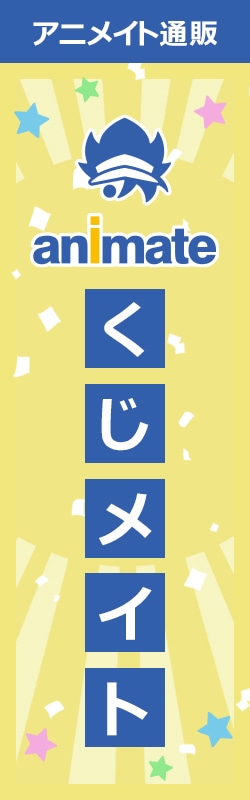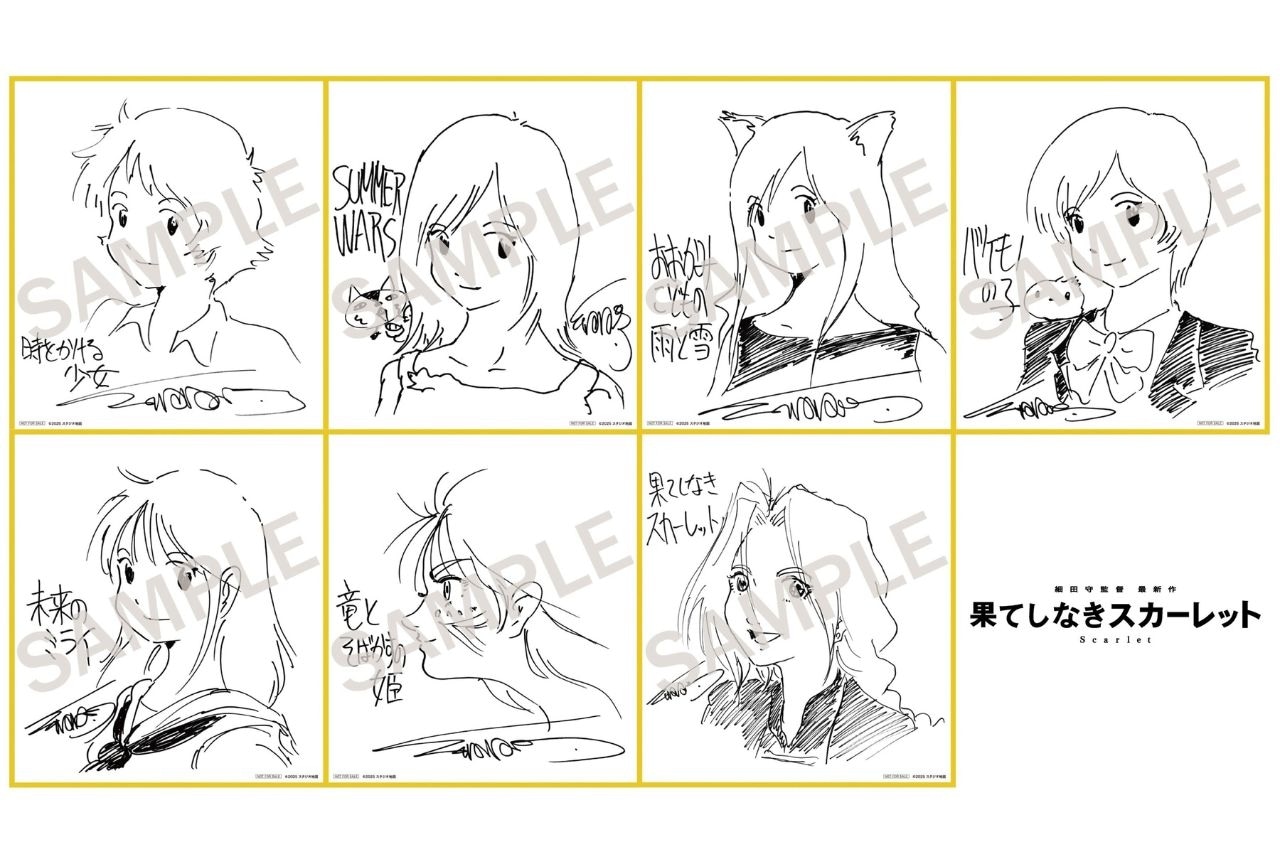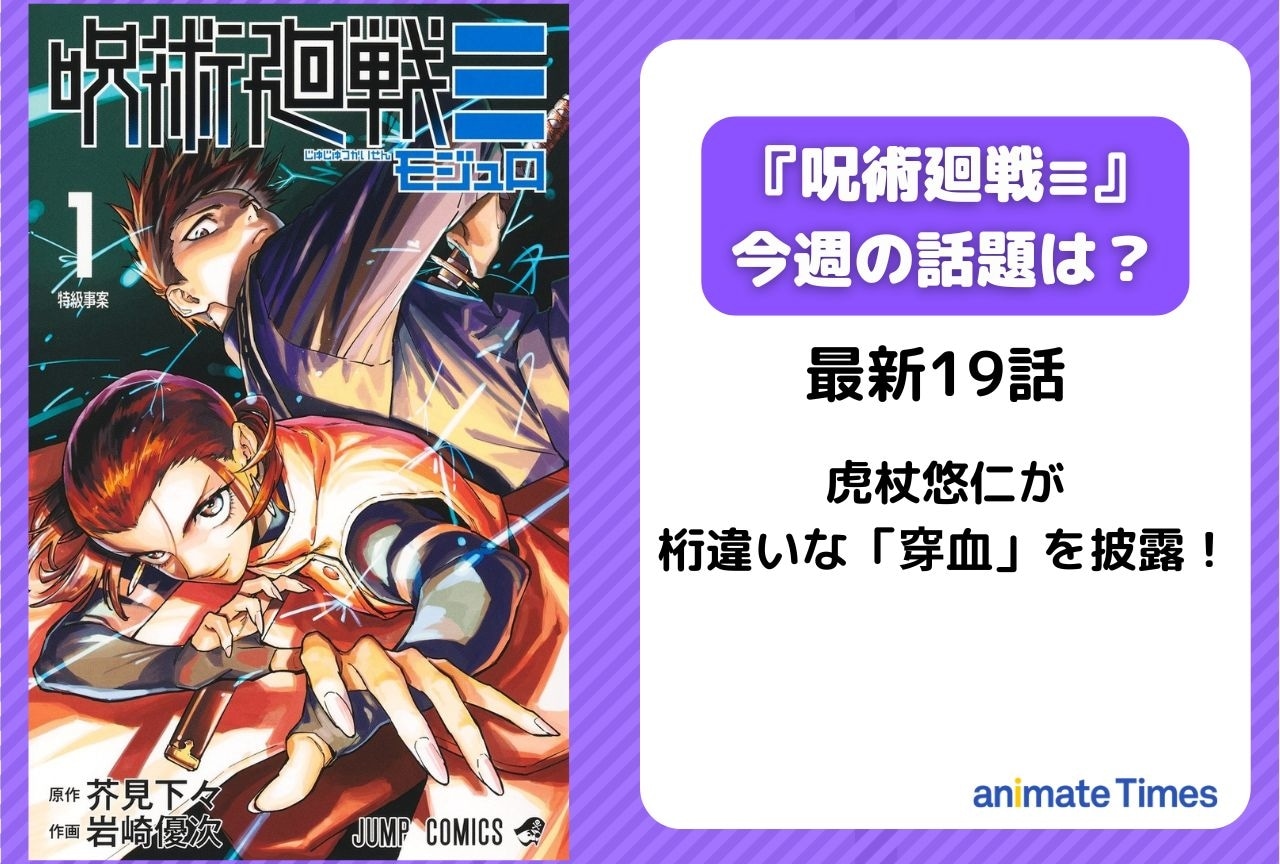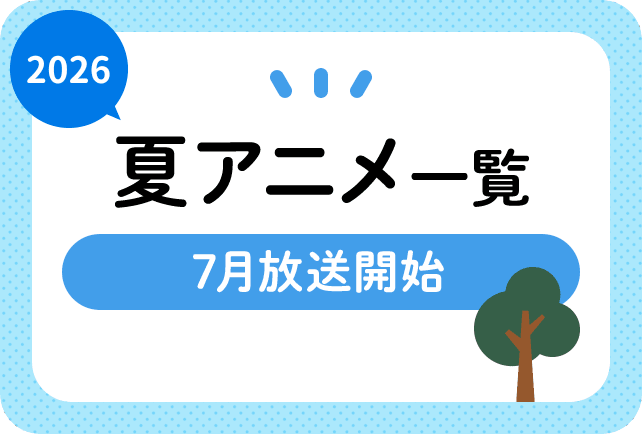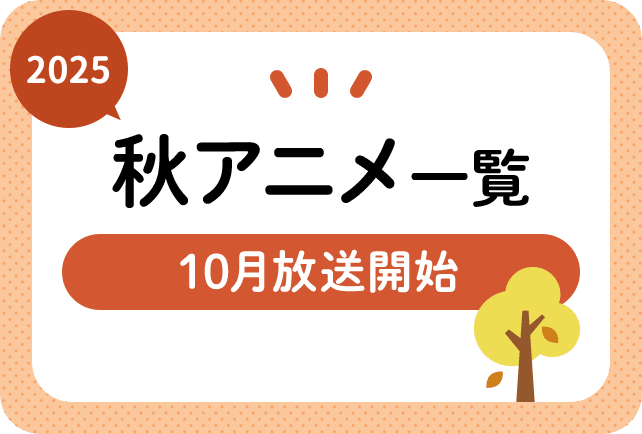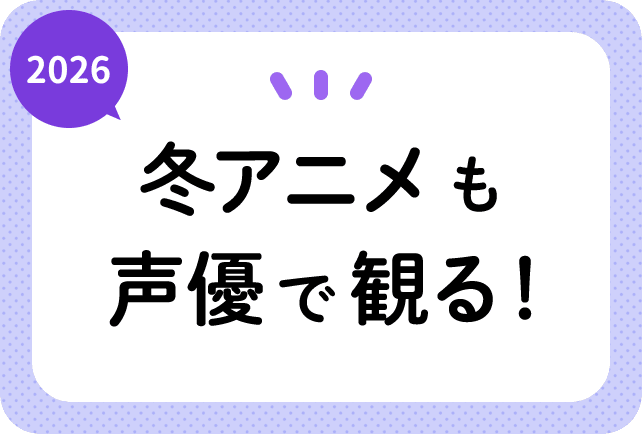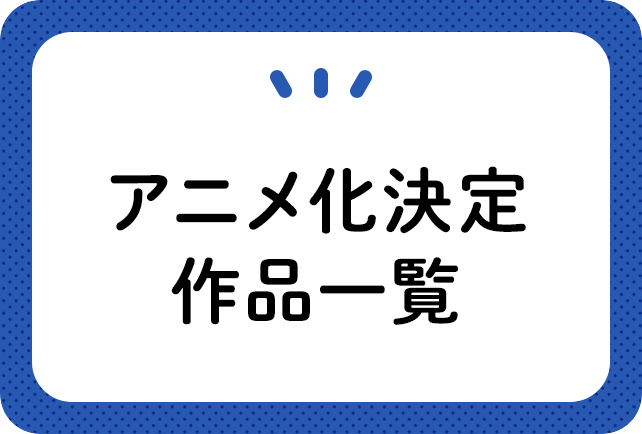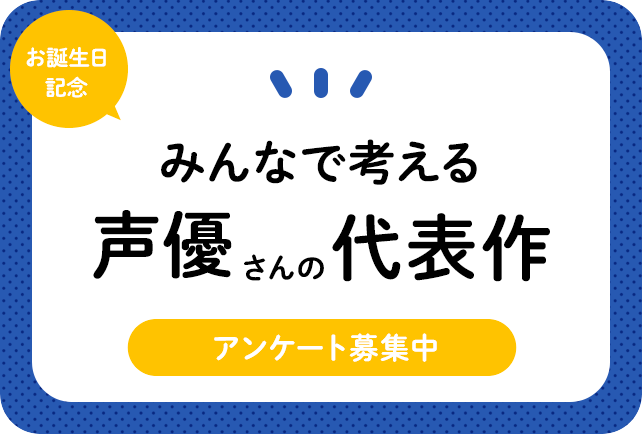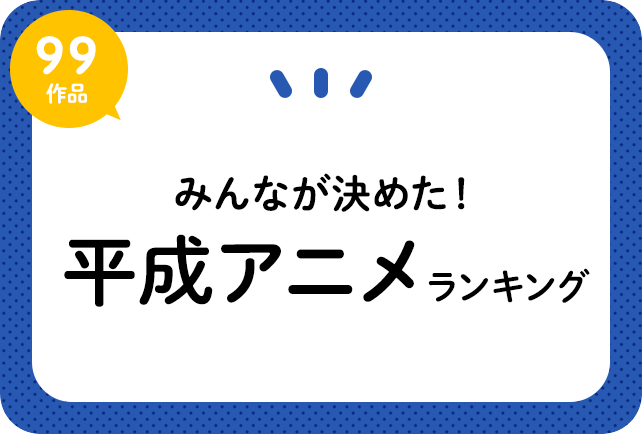『果てしなきスカーレット』細田守監督インタビュー|コロナで生死をさまよったからこそ生まれた死後の世界への描写、復讐の連鎖を断ち切るための「赦し」とは
古典『ハムレット』である意味
──復讐譚を描くということで、古典として『ハムレット』を選ばれた理由は何でしょうか?
細田:まず『ハムレット』という作品をこの映画のベースにしようと思った理由ですが、やはり復讐譚の元祖として、このテーマを考える上で避けて通れないものだったのが大きいです。特に、今の若い人たちが感じる不安や葛藤、悩みを代弁する物語として非常に適していると感じたんですね。
私が高校生から大学生の頃に読んだ『ハムレット』には、心に深く訴えるテーマがありました。ハムレット自身の年齢は劇中では30歳ほどですが、読んでいると若い頃の悩みや葛藤に寄り添う作品だと感じるんです。『果てしなきスカーレット』の主人公であるスカーレットは19歳という設定で、ちょうど人生をどう生きればいいのか迷う年齢です。そうした若い人たちの抱える不安や心情を『ハムレット』が400年経った今でも、人々の心に訴えかける普遍性を持っている作品だと思います。
そして私自身、戯曲を読むだけでなく、蜷川幸雄さんが演出され、渡辺謙さんが主演された『ハムレット』を舞台中継で観たことがあります。1988年のことなので、高校生だった私はその作品に衝撃を受けました。特に、オフィーリア役を演じられた荻野目慶子さんの素晴らしい演技が忘れられません。彼女の存在感は圧倒的で、一見するとただかわいそうなキャラクターですが、それだけではなく運命に負けない力強さが感じられました。当時私が最も印象に残ったのがそのオフィーリアだったんです。
今回の映画制作でも、そうした経験が影響しているのではないかと思います。ハムレットが本作では男性ではなく女性、つまりスカーレットとして描かれている点も、荻野目さんの演じたオフィーリアが与えた深い印象がどこか影響しているように感じます。運命の中でしんどい苦しみを抱え、狂気の中で死んでいくオフィーリアの姿。それは歴史の中で美しく描かれがちで、「川に浮かんでいる悲劇のヒロイン」というイメージで語られることも少なくありません。でも、果たしてそれだけで良いのか? という疑問はずっと持っていました。
もっと力強さをもって描くべきではないかという思いもあり、今回の映画のスカーレットにはそんな考えを反映させました。本作のポスターも、映画本編も、非常に力強さを感じさせる仕上がりになったと思います。そうした点でも私自身、過去に触れた『ハムレット』の影響が表れているのではないかなと思っています。
もちろん、これまでに様々な俳優がハムレットやオフィーリア、クローディアスなどのキャラクターを演じてきました。その解釈は舞台や作品ごとに違いますし、そこに多様性があるのが『ハムレット』の魅力だと思います。今回の映画のキャストには舞台経験の豊富な方々が多く参加してくださり、それぞれが個性的な解釈で役に臨まれたのではないでしょうか。
──海外の映画祭での反応はいかがでしたか?
細田:ヨーロッパの反応についてですが、感じたのは、やはり同じ作品でも受け取り方が異なるということです。日本では『ハムレット』というと教養や学問的なイメージが強く、「なんだか難しそうだ」と思われがちな一面があると思います。一方、ヨーロッパでシェイクスピアはもっと一般的な教養として捉えられています。向こうのジャーナリストからは、「この映画はアクション、ロードムービー、そして『ハムレット』を描いたものであり、非常にエンターテインメント性が高いですね」と評価をいただきました。日本では少し重厚で難解な作品として捉えられがちな『ハムレット』ですが、ヨーロッパではエンターテインメントの枠組みでも受け入れられているのだと実感しました。
また、ヴェネツィア国際映画祭に続きトロント国際映画祭でも上映させていただいたのですが、トロントでは『ハムレット』を題材とした映画がなんと4本もあったそうなんです。その中にはクロエ・ジャオ監督による新作『ハムネット』も含まれていましたね。この『ハムネット』というタイトルは、シェイクスピアの息子の名前からきており、その物語が描かれる作品です。
同時期に『ハムレット』をモチーフにした作品が複数制作されていることは、時代的な関連性を感じざるを得ません。本作を制作する際には、『ハムレット』に関連した作品が同時期に作られていることを当然知る由はありませんでした。映画祭のプログラムディレクターの方もこのような現象を興味深く感じていたそうです。
実はこれは珍しいことではなく、過去にも同じような状況が見られました。黒澤明監督が『蜘蛛巣城』を構想しはじめた時期には、オーソン・ウェルズも『マクベス』を題材にした作品を作り、さらにローレンス・オリヴィエも『マクベス』に取り組んでいました。おそらく、その時代において『マクベス』のテーマが必要とされていたのだと思います。こうした文化的な潮流や時代のニーズが、作品に影響を与える傾向があるのかもしれません。
ただ、それが何かを直接語り、関連付けるのは私たち作り手ではなく、むしろ観客の皆さんが考えてくださることでより正確に意味が生まれるのだと思います。
「赦す」ということ
──『果てしなきスカーレット』では復讐劇というテーマが大きな軸としてありながら、「赦す」「赦し」というキーワードも際立って強調されて描かれています。この「赦す」「赦し」という概念をここまで強調した理由についてお聞かせください。
細田:復讐をテーマとして考える中で、「赦し」という概念について向き合わざるを得ないことがありました。『ハムレット』を読むと父親の亡霊が息子ハムレットに「赦すな」と言いますよね。その言葉から復讐劇が始まるわけです。でも、もし父親が逆のことを言ったらどうなるのだろうかと考えたんです。これが非常に悩ましい問いになると思いました。
なぜなら、「赦すな」と言われるほうがある意味では分かりやすいんです。当然の感情として憎しみや怒りが湧き、それをエネルギーとして復讐に向かうことができるからです。そんなひどい相手をどうして許せるのか、と。そしてその問いが生まれることで、さらに深い葛藤が生じることになると感じました。
この話は先ほどお話しした報復の連鎖ともつながっていますね。復讐のサイクルを続けていては、結局際限がなく終わらない。どちらかが「赦す」という行為を選ばなければ、その連鎖を断ち切ることはできないという問題があるわけです。しかし、現実はそんなに簡単ではありません。誰かにひどいことをされたとき、その相手をすぐに許せるかといえば、そんなことはほぼ不可能だと感じます。私たちももし同じ目に遭ったら、許すことの難しさを痛感するでしょう。
それでも、その復讐の連鎖を続けることで人生を使い果たしてしまうのか、それともそれを乗り越えて違う未来に目を向けるのか。どちらを選ぶかで人生は大きく異なるものになると思います。制作を進める中で、この問題に何度も向き合うことがありました。特に自分自身の状況を想像したとき、自分の娘が私のために復讐をしようとしたらどう思うだろうか、と考えました。
父親としては、間違いなく「やめてほしい」と思うでしょう。復讐を果たそうとする気持ちは感謝するかもしれません。でも、それよりも娘には自分自身の人生を大事にしてほしい。そのほうが父親としてははるかに嬉しいと思います。復讐心を持って生きる人生は、決して良いものではない、そう感じます。
しかし、それは自分の気持ちであって、子供や他者がどう感じるかは別問題です。そこが復讐というテーマの難しさであり、恐ろしさでもあると感じますね。復讐を目的に生きることで、その人の人生が消耗されてしまい、結局何も得られないのではないか、そんな気がしてなりません。
そのようなことを考えながら、映画の中でも主人公たちの葛藤や選択を描きました。「生きるべきか死ぬべきか」という問いを、主人公のスカーレットと聖の関係に置き換え、物語のラストで表現したつもりです。このテーマはとても重いですが、それでも復讐劇を通じて浮かび上がる人間の姿や感情は観る人に問いを投げかける力を持っていると思います。
もちろん、このテーマに対する捉え方は人それぞれです。「最も憎い相手を許すこと」が真の許しだと考える人もいるでしょうし、別の価値観で解釈する人もいるでしょう。ですので、映画を観た皆さんには、自分にとっての「赦し」とは何か、自分ならどうするかということを考えていただければと思います。何が正解かということを提示する映画ではありません。むしろ自由に感じ取っていただくことを目指して作りました。
死後の世界は監督のとある体験が……
──本作では死後の世界が描かれていますが、今回描かれた死後の世界には、監督ご自身の死生観が反映されているのでしょうか?
細田:今回の映画では確かに「生と死」という非常に大きなテーマに挑むことになりました。正直、ここまで壮大で重いテーマを扱うことになるとは思っていませんでしたが、振り返ってみるとこれまでの作品の中でも生と死というモチーフに少なからず触れてきた部分があると思います。そうしたテーマが今回の作品ではより表面化し、スケールの大きな映画になったのではないかと思います。
きっかけとして、やはり自分自身が体験した「死に向き合う瞬間」が挙げられます。それは、コロナに感染して入院したことです。コロナで入院した人は分かると思うのですが、入院してから最初の1週間が特に重要で、その期間で病状が悪化するか改善するかで人生が大きく変わる。私もその不安を抱えながら過ごしました。
コロナに感染したのは『竜とそばかすの姫』を制作している最中で、まだ完成していないタイミングだったので、非常に大きな不安に直面しました。もしものことがあったら、誰が完成させてくれるのだろうか……。そんな思いが頭をよぎりました。幸いにも私は1週間後には改善し、回復することができました。ただ、その入院期間中に死と隣り合わせの状況にいるという現実を目の当たりにする瞬間もありました。
また、その入院中に感じた看護師さんたちの存在が非常に大きかったんです。病院の先生以上に、看護師さんが支えてくださる場面が多くありました。防護服で顔も見えない状況ではありましたが、その人の優しさや温かさは伝わってきました。看護師という職業に就くためには、単なるスキルだけではなく、深い思いやりや人間性が必要な才能だとも感じました。彼らの利他的で献身的な患者へのケアには大変感謝していますし、非常に感動しました。
そこで今回の映画で描いた主人公のスカーレットと彼女を支えるもう一人の主人公、聖というキャラクターにも、この看護師という存在が影響を与えていると思います。スカーレットは現実主義的な復讐者に対して、聖は理想主義的な看護師という対比的な人物として描かれています。この対比が物語の中で非常に重要な要素となっています。
──そんなことがあったんですね……。また、≪死者の国≫の世界観がどのようにして形作られたのかについてもお聞かせください。
細田:『ハムレット』でも「黄泉の世界」が存在することが描かれています。父親の亡霊がハムレットに語りかけるシーンなどもその一例です。この物語における死後の世界の存在感というものが、今回の映画においても重要な影響を及ぼしていると思います。
今回、地獄の描写について考える際に、日本の地獄絵図が参考になりました。私は日本美術の研究者の方とも議論し、中世に描かれた地獄絵がどのように表現されているのかを尋ねました。日本の地獄絵図にはたくさん種類がありますし、日本の文化には山岳信仰もあって、地獄や霊的な信仰の対象となるような山々も存在します。実際、私の故郷である富山にも千年前からの山岳信仰を受け継ぐ地域があり、その中で地獄がどのように捉えられてきたのか、原体験としても地元の文化の中で知ることができました。
その日本美術の研究者が非常に興味深いことを教えてくれたんです。日本の中世の地獄絵図は、「地獄のように見えて、実は現世を描いている」という話です。つまり、地獄が異世界ではなく、この現世の苦しさを表現しているというんです。最初は驚きましたが、よくよく考えるとすごく納得できました。「鬼が人を苦しめる」とか「殺伐とした景色」といった描写は、「地獄で起きること」ではなく、「この世に存在する苦しさの象徴」だということ。現世が地獄だと思っている人には、まさに今生きているこの場所が地獄なんですよね。逆に楽しい人生を送っている人には地獄だとは感じられない。それを聞いたとき、「なるほど」と思いました。
考えてみればニュースを見ていて、紛争地などをレポートする際に「まるで地獄のようです」と表現されることがあります。現世にも地獄のような状況は存在していて、そうした環境で私たちは生きている。そこで、魂が天国に行けることを願っている人々もいる。それなら、死後の世界を単なるファンタジックな地獄として描くのではなく、むしろ現世の延長として描くべきだと思ったんです。
その考えを基に、私はロケハンのためにヨルダンやイスラエルに訪れ、現地の状況を体験しました。ヨルダンでは荒野の中で、宗教の原点となった風景を見ることができました。イスラエルでは一神教の聖地を訪れただけでなく、壁の向こう側にも足を運びました。実は、渡航禁止になる直前のタイミングだったのでギリギリで見ることができました。こうした宗教的背景が形作られた地や風景を直接体験したり、見ることができたのは非常に貴重な体験でした。その体験が映画の世界観、≪死者の国≫に反映されている部分があると感じています。