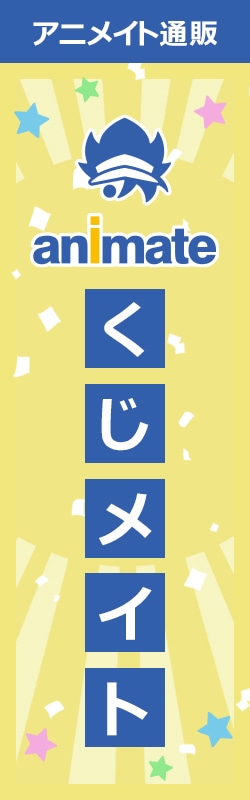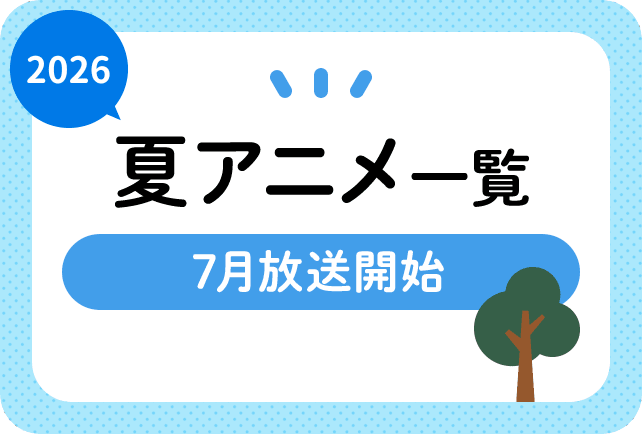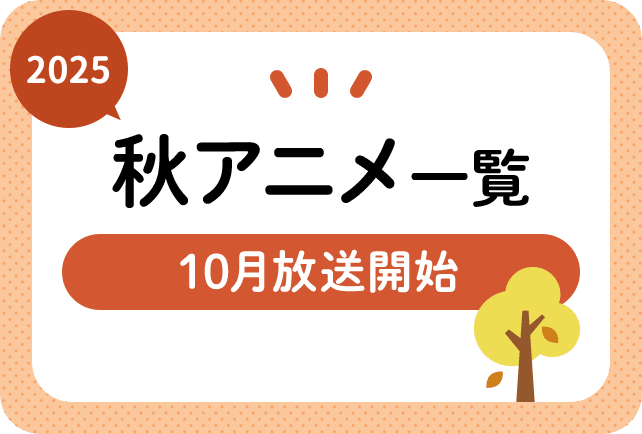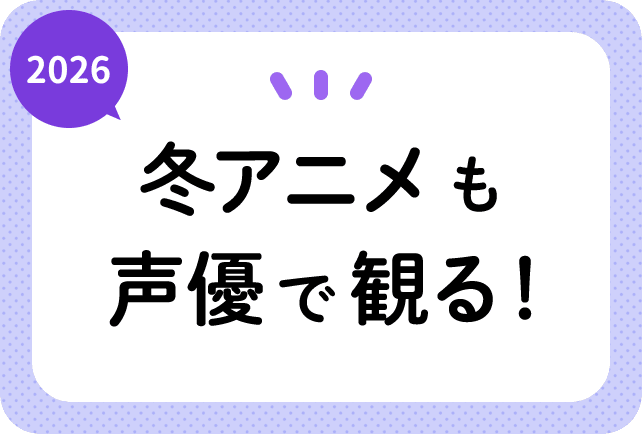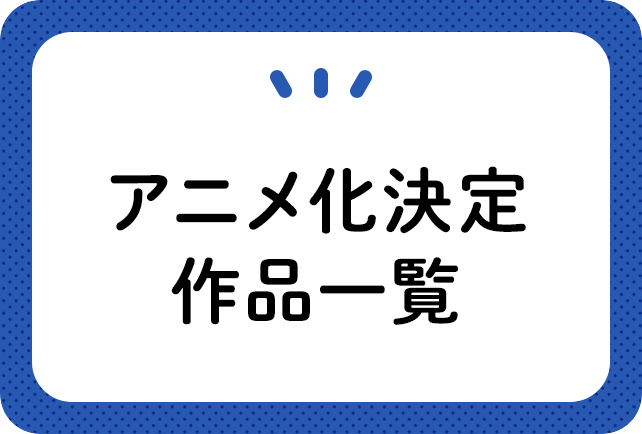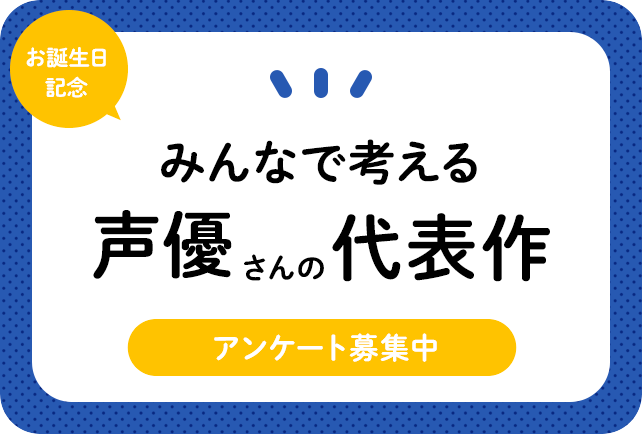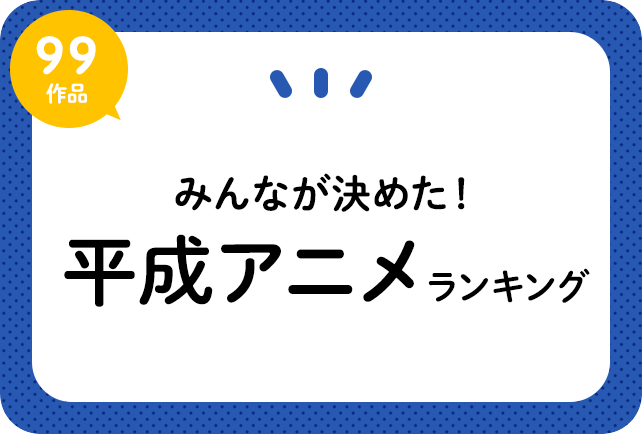秋アニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』古屋亜南さん・島﨑信長さん・斉藤壮馬さんインタビュー|“音楽で世界を救う”新世代ヒーローのドラマ――
古屋くんの努力する姿が、物語ともすごくリンクしていた
──演じるうえで、どのようなディレクションがありましたか?
古屋:第1話でキョウヤが凪におにぎりを渡すシーンがあるのですが、そのとき「キョウヤはおばあちゃん子で、自然に優しさがあふれ出る子。押し付けるような優しさは出して欲しくない」というディレクションをいただいたんです。恥ずかしい話、声優という仕事をこれまでやってきて、そういったディレクションを受けるのが初めてだったので、「押し付けない優しさとは何か」と演じているときにずっと考えていました。
何テイクか重ねるなかでOKが出たのですが、後日、監督から「もう少し粘りたい」と言っていただいて、もう一度録りなおしたんです。そのときは少しアフレコも進んでいて、自分のなかでもキョウヤに対する理解度が深まっていました。それもあってか、監督から「本当に古屋さんのなかで生まれたキョウヤが自然に出た形になったと思います」と録りなおしたあとに言ってもらえたんです。ものすごく嬉しかったですね。
島﨑:わりとお任せいただいて演じていたのですが、表現の仕方を「もう少しこういう方向で」というリクエストをいただくことが何度かありました。こちらが提示したものに対して、「こっちの方向でお願いします」という演出をしっかり伝えてくださるので、非常に演じやすいですね。
斉藤:先ほどもお話したように、序盤では彼自身の我を押し出していくというよりは、個性的な面々を「まあまあ」となだめるようなお芝居を要求されていた印象があります。「もっとキラキラ王子様系で」というディレクションをいただいたことがあるのですが、それがどういう風に効いてくるのかは、この先の展開で感じ取っていただければと思います。
──アフレコ現場はどんな雰囲気ですか?
古屋:香盤表を見たとき、大先輩の方々の名前がパッと目に入り、とにかく置いて行かれないように、しがみついていかなきゃという気持ちにとらわれてしまったんです。それで変に準備していって、自分のなかで凝り固まったイメージのキョウヤを演じてしまいました。そのなかで、島﨑さんと斉藤さんが今と同じ様に横に座ってくださって、僕にとっては金言でしかないアドバイスをたくさんくださったんです。自分だけ居残りで収録するときも、お二人は別の予定があるにも関わらず、ギリギリまで僕のことを後ろで見てくださいました。勝手ながら師匠や兄がいたら、こんな感じなんだろうなと思っていたんです。心強かったですね。
島﨑:後ろで見ていたとき、自分たちの先輩もこういう気持ちだったのかなと思っていました。あと、古屋くんのそういう努力する姿が、物語ともすごくリンクしていたんですよね。新生「SI-VIS」はまだちぐはぐしていて、バラバラ感も否めないかと思いますが、キョウヤは頑張ってコミュニケーションを取って、みんなとつながっていこうとします。その姿や展開と、古屋くんの頑張り・現場の結束が固まっていく感じが重なって見えました。これって、毎週顔を突き合わせて、みんなで同じ空間で収録できたからこそ起きたことだと思います。やっぱり、アフレコ現場っていいなと思いました。
斉藤:ディレクションに対して素直であることは大切だとは思いますが、亜南くんは同時に、言われたことに対してどう芝居にフィードバックさせるべきなのかを、自分なりに咀嚼しているんです。それがすごく素敵だなと思いました。信長さんがおっしゃるように、キョウヤの成長とともに亜南くんがスキルを身につけているとも感じました。この先の話数で、キョウヤとJUNEの大事なシーンがあるんです。僕は出る時間が決まっていたのですが、そのシーンは絶対にOKテイクが出るまではいたいと思って、最後まで一緒にいました。無事次の現場にも間に合いました(笑)。
古屋:その節はどうもすみませんでした!
斉藤:でも、同じ場所、同じ時間を共有できてよかったなと思えるような、すばらしい芝居を亜南くんがしてくれたんです。
島﨑:どのシーンなのかは、見たら絶対に分かるはず。あのシーンは、壮馬くんもがんばっていました。ふたりのがんばりをみなさんにもはやく届けたいです。
「台本を見ず、映像だけ見てやってみよう」という提案がスタッフさんからあって
──3話ではキョウヤが加入し、新生「SI-VIS」が動き出しました。ここまでの物語を振り返ってみて印象に残っているシーンやアフレコ時の思い出を教えてください。
古屋:第3話でキョウヤが大泣きするシーンは、監督たちに付きっ切りになっていただいて、何テイクも重ねて収録したんです。なかなか表現が上手くできず時間がかなり経ったときに、「台本を見ず、映像だけ見てやってみよう」という提案を音響監督からいただいて。そうして練り出したものを「OKです」と言ってもらえたんです。必死過ぎて正直そのときの記憶が曖昧ではあるのですが、やりきったという気持ちは覚えていて。印象深いシーンです。
島﨑:第2話以降を見ていると、YOSUKE以外の人とソウジが接するときの態度が違うというのが分かるんです。“YOSUKEの前でしか見せないソウジ”というのがあるんですよね。ソウジは一人で立ち上がり、自立したがるタイプですが、YOSUKEだけにはどこか頼っている部分があって。ライバルでもあるけれど、この人に認められたいという想いが見え隠れしているんです。
直情的ではあるソウジですが、YOSUKEの前で見せていた“照れ”は、他の人には今のところ見せていません。YOSUKEの登場自体は短かったですが、ふたりのやり取りから積み重ねを感じました。
斉藤:僕もYOSUKEの存在が印象に残っています。ここからの先の物語でも、YOSUKE がそれぞれの心のなかに居続けることで、各々が変化したり、成長に繋がったりしてくるんです。YOSUKEがいないことをどう受け止めていくのか、それぞれの向き合い方が重要なポイントのひとつにもなってくるので、そういう点からもYOSUKEの退場は非常に印象的でした。
──本日はありがとうございました。最後に、改めて今後の見どころをお聞かせください。
古屋:アフレコ前に台本をもらうたびに、衝撃がすさまじかったです。ここまでの物語のなかでも、色々と不穏な空気が流れていたと思いますが、ここから先で何が起きて、どこに着地するんだろうと考えを巡らせながら、作品を楽しんでいただけたら嬉しいです。
島﨑:スケールが大きかったり、煌びやかだったり、グーンと暗い方向に話が進んだりするなかでの細かい人間模様が、個人的には本作の面白さのひとつだと思っています。1話進んだら、あのキャラクターのあの人への態度や言い方が変わっているなど、積み重ねを感じられるんですよね。その辺も余すことなく楽しんでもらえたらと思います。
斉藤:いよいよ本格的に物語が大きく展開していきます。個人的に、ここから先の話数で大きなパラダイムシフトと言いますか、「そういう世界だったのか!」と、驚きと衝撃を受けた回があるので、そこまで色々と考察しながら楽しんでいただきたいです。
[文・M.TOKU / 写真・MoA]
作品情報

あらすじ
キャスト
(C)2025 ハルモニアエンタテインメント